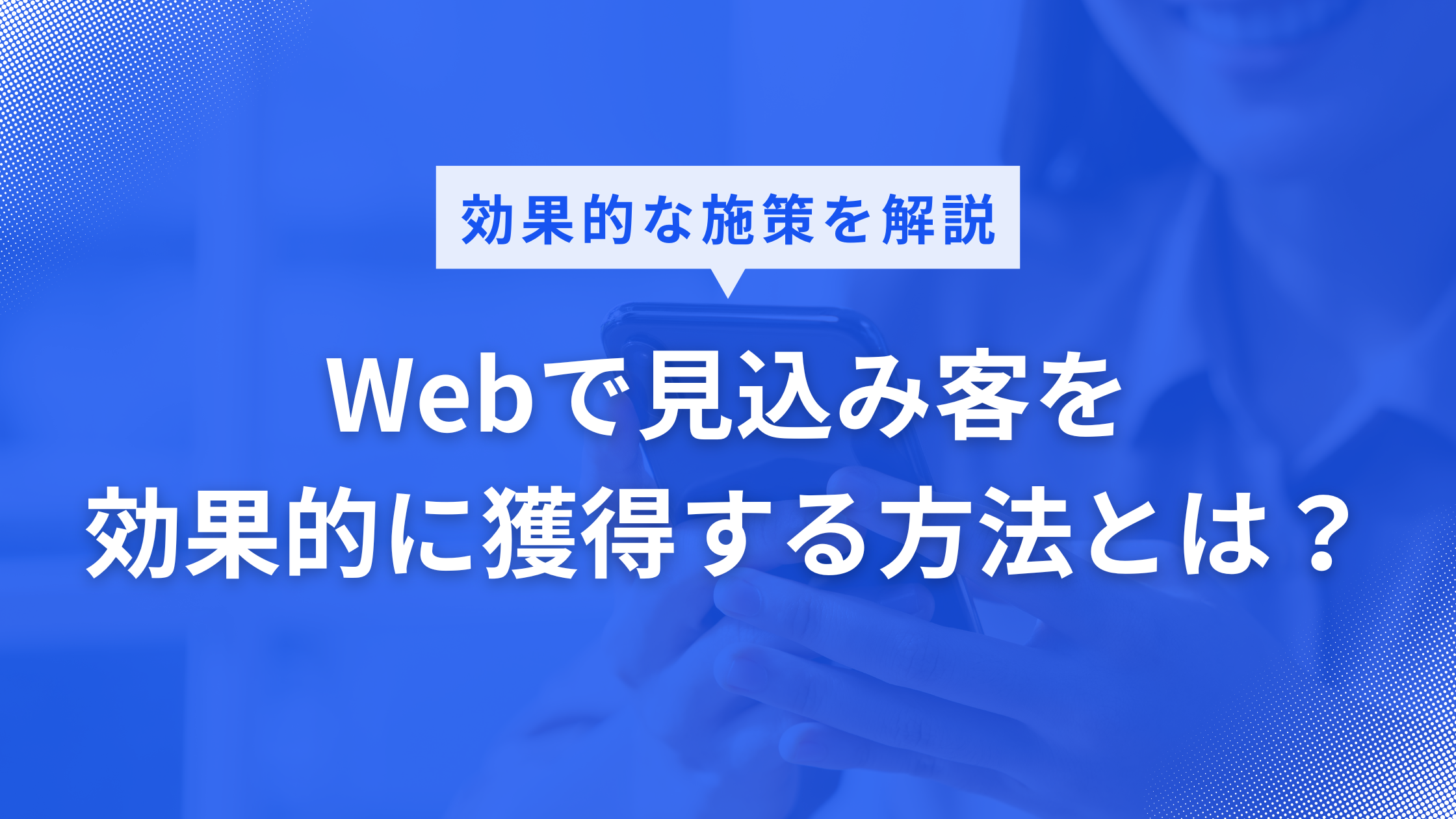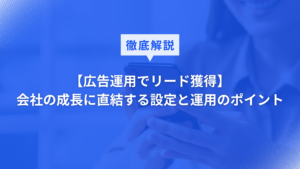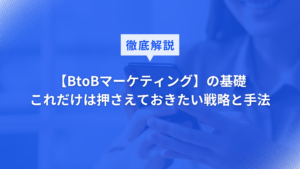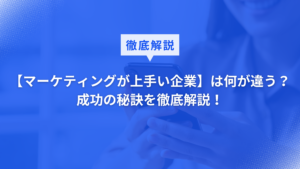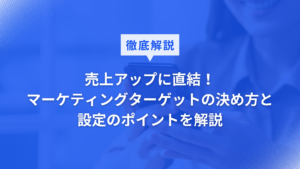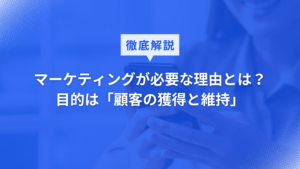第1章|Webリード獲得の基本構造とBtoBにおける重要性
1-1. Webリード獲得とは?
Webリード獲得とは、Web上で見込み客(リード)を集めることを指します。
具体的には、以下のような行動を取ったユーザーをリードと定義します。
- 資料請求をした
- ホワイトペーパーをダウンロードした
- お問い合わせフォームを送信した
- 無料相談に申し込んだ
- メルマガに登録した
こうした行動の背後には、「何らかの課題を感じている」「情報収集中である」「解決策を探している」といった動機があります。
特にBtoB領域では、顧客単価が高く、検討期間も長いため、この“リードの入口”が商談や受注に直結する極めて重要なファーストステップになります。
1-2. なぜ今、Webリード獲得が注目されるのか?
かつての営業は「展示会」「テレアポ」「飛び込み営業」など、オフラインの接触が主流でした。
しかし現在、見込み客の行動は大きく変化しています。
📱 顧客の購買行動は“検索”から始まる
BtoBの意思決定者も、まずはGoogleで検索します。
「〇〇 業務効率化」「〇〇 比較」「〇〇 導入事例」など、課題に紐づくキーワードで情報収集をし、必要そうなサービスを検討し始めるのです。
📉 オフライン営業だけでは限界がある
- テレアポのつながり率は年々低下
- 飛び込みは迷惑がられる時代に
- 展示会もターゲットが限定されがち
こうした背景から、“相手から能動的に来てもらえる仕組み”=Webリード獲得が企業成長の要になっています。
1-3. BtoBにおけるリードの特徴
BtoBのリードは、BtoCと異なり以下のような特徴があります:
| 比較軸 | BtoC | BtoB |
|---|---|---|
| 購買決定 | 個人 | 複数名の合議制 |
| 検討期間 | 短い(即決も多い) | 長い(1ヶ月〜半年以上) |
| 購買動機 | 感情・体験 | 業務課題・コスト改善 |
| 平均単価 | 数千円〜数万円 | 数十万円〜数千万円 |
| 営業手法 | 商品理解重視 | 信頼関係・課題解決重視 |
つまりBtoBでは、「見込み客の育成(ナーチャリング)」「継続的な接点設計」「教育型コンテンツ」が必要不可欠になります。
1-4. リードの種類を理解する:顕在層と潜在層
BtoBマーケティングで最も見落とされがちな視点が、「リードの温度感=見込み度の違い」です。
| リード層 | 状態 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 顕在層 | 課題を明確に認識しており、解決策を探している | 「営業代行 比較」などの検索をしている | 競合との比較検討段階、CPAが高騰しがち |
| 準顕在層 | 課題を感じ始めているが、まだ調査段階 | 「営業成果が上がらない理由」などの調査中 | 教育で興味を高めることができる |
| 潜在層 | 課題にすら気づいていない、無関心層 | 「社内が停滞していると感じる」など漠然とした不満 | 潜在層攻略が差別化とLTV向上の鍵 |
特に、BtoBでは上記3層のうち、潜在層〜準顕在層がリードの7割以上を占めるとも言われています。
この層をどうやって教育し、信頼を得るかがWebマーケティングの勝負どころになります。
1-5. Webリード獲得の基本構造
以下の3ステップで、リードを獲得→育成→成約へと導く設計が求められます。
① リードの入り口をつくる
- ホワイトペーパーのDL
- 成功事例集
- チェックリストや無料診断ツール
- セミナーへの登録
💡 ポイント:メールアドレスだけなど、“軽いアクション”で済むものから設計することで、潜在層にもアプローチしやすくなります。
② ステップメール・情報提供で教育
- なぜその課題が起きているのか
- 他社事例や失敗パターン
- 自社の価値観や取り組み
💡 ポイント:「セールス」ではなく「共感」や「納得」を育てる設計を重視します。
③ 商談化・受注へ
- 無料相談・戦略設計の案内
- 初回提案資料の提示
- 事例を元にしたシミュレーション提供
💡 ポイント:この時点で課題理解と信頼が深まっていれば、クロージング率は高まります。
1-6. 「広告で顕在層を狙えばリードが取れる」という時代は、もう終わっている
かつては「リスティング広告さえ打てば、それなりにリードが獲得できた」という時代がありました。
しかし今では、あらゆる企業が「営業代行 比較」「MAツール 導入」などの顕在キーワードに広告を出しており、入札単価は高騰し、CPAは悪化の一途をたどっています。
さらに顕在層は、「価格」「機能」「営業対応」など、表面的な比較で判断されやすく、差別化が困難です。
✅ SNS・オウンドメディア・YouTubeで、有益な情報を“自ら発信”する時代へ
変化に気づいた経営者たちは、今や自ら情報発信し、潜在層との信頼関係を築くことに力を入れています。
- LinkedInやX(旧Twitter):業界の知見や経営の考え方を発信し、共感を得る
- noteやブログ:ノウハウ・裏話・業界課題をオープンにすることでSEOと信頼を獲得
- YouTube:実績紹介・HowTo・社風を動画で伝え、感情に訴える
特にYouTubeは、文章だけでは伝わらない「温度感」や「現場のリアル」を届けられる強力なメディアです。
企業の想いや信念を動画で伝えることで、まだ課題を自覚していない潜在層にまでリーチでき、見込み客としての関係構築が始まるのです。
「この会社、信頼できそうだな」「この考え方、共感できる」
そう感じた人たちが、顕在化する前にファンとなり、気づいた時には「他と比べる必要がない」と選ばれる。
それが、広告では買えない“信頼”を資産として積み上げるマーケティングです。
今、Webリード獲得に本気で取り組むなら、「顕在層だけを狙う」という発想は捨てるべき時期に来ていると考えられます。
第2章|なぜ潜在層の攻略が成果の分かれ目になるのか?
「なぜうちは広告を出しても反応が薄いのか?」
「なぜ競合より優れたサービスなのに選ばれないのか?」
このような疑問を抱く企業は多くあります。
その根本的な原因のひとつが、“顕在層しか狙っていない”という戦略の限界にあります。
BtoBマーケティングにおいて成果を最大化するには、「潜在層をどう取り込むか?」という視点が必要不可欠です。
2-1. 潜在層の方が「母数が圧倒的に多い」
そもそも、顕在層とは「すでに課題を自覚しており、解決策を探している層」を指します。
言い換えると、検索して比較して、どの会社にするかを選んでいる人たちです。
たとえば、あなたのサービスが「営業代行」だったとしましょう。
「営業代行 比較」「営業代行 導入費用」などと検索している層が顕在層です。
一方、潜在層とはこういった層です:
- 「営業がうまくいかないけど、何が問題かわからない」
- 「新規事業を始めたけど成果が出ない…」と悩みながら検索する
- 「採用した営業が定着しない」「営業マネージャーが育たない」など
つまり、まだ「営業代行を入れよう」とは考えていないが、根本的な課題は抱えているという層です。
ここが非常に重要なポイントで、実際にマーケティングリサーチや購買行動分析のデータでも、顕在層:潜在層=3:7 または 2:8とも言われています。
つまり、潜在層を取り込める企業こそが、シェアの7〜8割を支配できる可能性を持つのです。
2-2. 顕在層は“価格競争”に巻き込まれる
顕在層を狙うマーケティングには、以下のような構造的な限界があります。
✅ 競合との比較が前提
顕在層は「すでに情報収集を始めている」ので、他社の情報にも同時に触れている状態です。
検索結果や比較サイトには、価格・実績・機能などが並び、どうしても“横並び”の勝負になってしまいます。
✅ 差別化が難しい
「うちは対応が丁寧です」「品質が高いです」などの言葉は、競合他社も同じように言っています。
差別化要素が曖昧であればあるほど、最終的には“価格”が選定要因になりやすくなってしまうのです。
✅ CPAが高騰する
競合も同じキーワードに入札しているため、広告費はどんどん高くなり、「獲得単価が合わない」「採算が取れない」状態に陥るのです。
2-3. 潜在層は“価格ではなく、信頼で選ぶ”
潜在層はまだ「何を買えばいいのかすらわからない」状態です。
だからこそ、“課題を言語化してくれる存在”に出会うことで、信頼を感じやすくなります。
ここで重要なのが、コンテンツによる「気づきの提供」です。
たとえば──
- 「成果が出ない営業組織に共通する5つの構造」
- 「“検討します”で終わる営業がなぜ続くのか?」
- 「営業代行が機能しない会社の特徴」
このような顧客自身が気づいていない“本質的な課題”を見せるコンテンツは、非常に強力です。
なぜなら、顧客にとっては「そうか、だから今のやり方ではうまくいかないのか」と、目の前の霧が晴れるような感覚になるからです。
その結果、見込み客は「この会社なら、信じて任せられそうだ」と思うようになります。
つまり、潜在層に選ばれる理由は“価格”ではなく、“信頼”や“共感”なのです。
2-4. 潜在層を先に教育すれば、“競合不在の状態”で商談が始まる
ここが、BtoBマーケティングの隠れた“最強の勝ち筋”です。
潜在層に対して、「なぜ成果が出ないのか」「どこから着手すべきか」を自社独自の視点で情報提供しておくと、見込み客は“その考え方の信者”になっていきます。
そして課題を自覚したとき、
「すでに考え方を学んできたこの会社に相談しよう」と思うようになるのです。
これは競合比較とはまったく異なる心理状態です。
- 比較せず
- 値引き交渉もされず
- 自然に商談が始まり
- 高確率で契約に至る
この状態をつくれるのが、潜在層マーケティングの最大の強みなのです。
2-5. 潜在層はLTVが高く、長く続く関係になる
さらに注目すべきは、潜在層から獲得した顧客の“定着率”や“LTV(顧客生涯価値)”が高いということです。
顕在層で獲得した顧客は、たまたま時期が合っただけだったり、比較して最安値だったからという理由もあります。
そうした顧客は、より安いサービスが出てきたらすぐに離れる可能性があります。
一方、潜在層から獲得した顧客は、
- 思想や価値観に共感している
- 教育されて納得して契約している
- 自社に期待してくれている
という背景があるため、契約後の満足度が高く、継続率も高くなりやすいのです。
2-6. 潜在層の獲得が、採用やパートナー開拓にも波及する
潜在層への価値提供は、見込み客だけでなく「一緒に働きたいと思う人材」や「協業を希望するパートナー企業」にも波及します。
- 「この会社の思想に共感した」
- 「この考え方で営業をやってみたい」
- 「自社のクライアントにも紹介したい」
そんな声が届くようになり、ビジネス全体の“求心力”が高まっていくのです。
まとめ:潜在層を獲得できるかどうかが、成長曲線の角度を決める
BtoBマーケティングにおいて、「成果が出ている会社」と「打っても響かない会社」の差は、
潜在層にアプローチできているかどうか──これに尽きます。
顕在層だけを狙っていては、競合と横並びになり、消耗戦になります。
一方で、潜在層のうちから信頼を育てておけば、競合比較を受けずに選ばれる存在になることができます。
この“選ばれる構造”こそ、成果を安定的に積み上げていく仕組みの土台となるのです。
第3章|BtoB企業が潜在層を獲得するための具体戦略
潜在層を攻略するには、単に「広告を出す」だけでは成果は出ません。
重要なのは、“今すぐ客ではない人”との信頼をどう構築するか?です。
この章では、BtoB企業が実践すべき「潜在層を獲得するための6つの具体施策」と、それを支える考え方を解説します。
3-1. 有益な“教育コンテンツ”を提供する
潜在層の関心は、「○○を導入したい」ではなく、「今の状態、なぜうまくいかないんだろう?」です。
つまり、いきなりサービス紹介をしても刺さりません。
そこで有効なのが、教育型のコンテンツです。
これは、顧客がまだ気づいていない“課題”や“誤解”を明確にし、気づきと学びを与えるものです。
例:
- 「なぜ営業代行が機能しないのか?」
- 「成果が出る営業には、実は“仕組み”がある」
- 「検討され続けて終わる営業の構造とは?」
コンテンツの形式は、ブログ・ホワイトペーパー・note・PDFレポート・動画など様々ですが、重要なのは“教育”を目的とした切り口です。
3-2. メールアドレスやLINEで取得できる「軽いLP」を設ける
BtoBの潜在層は、個人情報の提出に慎重です。
会社名・電話番号・部署名などが必須のLPでは、反応率が極端に下がってしまいます。
そこで有効なのが、「メールアドレス」あるいは「LINEアカウント」でリードを取得する“軽いリード獲得LP”です。
現在ではLINEのビジネス利用も浸透しており、
「メールよりも開封されやすい」「1対1感がある」「気軽にブロックできるため心理的ハードルが低い」などの理由から、ライトな関係づくりにはLINE誘導が非常に有効です。
軽いLPの構成要素:
- 共感を生む問題提起(例:「やってみたけど成果が出ない営業に終止符を」)
- 教育価値のある資料や無料診断コンテンツの紹介
- メールアドレスまたはLINEで登録可能なシンプルフォーム
💡 ポイント:リード獲得の初期段階では、「とにかく接点を増やす」ことが最優先。
個人情報を深く取りすぎず、まず“関係を始める”ことにフォーカスしましょう。
✅ リスト管理の重要性
獲得したリード情報(メールやLINE)をきちんと管理できていなければ、どれだけ見込み客がいてもビジネス成果にはつながりません。
- 誰が何に興味を持ったのか
- どのタイミングで資料をDLしたのか
- ステップメールはどこまで読んだのか
- LINEで何をクリックしたか
こうした情報を一元管理できる仕組みを整えることで、タイムリーなアプローチや営業連携が可能になり、受注確率を大きく高めることができます。
CRMやMA(マーケティングオートメーション)ツールの導入はもちろん、
「このリードに、次に何をすべきか」が見える状態を常にキープすることが、潜在層攻略では不可欠です。
3-3. ステップメールで「思想」と「信頼」を届ける
ダウンロードして終わり──では意味がありません。
ここからが“勝負”です。
ステップメールとは、あらかじめ設計された一連のメール配信を通して、顧客の理解や信頼を育てていく手法です。
役割:
- 共感を呼ぶ(課題の整理)
- 「なぜうちは失敗していたのか?」という気づき
- 他社事例・成功例による信頼形成
- 自社サービスのポリシー・価値観の提示
- 初回相談・無料診断への案内
ここでは、売り込みではなく「この会社、誠実でわかってくれるな」と思ってもらえることが最優先です。
3-4. YouTube/動画コンテンツで「顔の見える情報発信」
文字情報だけでは伝わらない熱量や信頼感は、動画で一気に伝わります。
特にYouTubeや動画配信は、社長の考え方、社風、現場の様子、事例紹介など、感情を動かすには非常に有効です。
BtoBで効果的な動画内容:
- 「失敗する営業代行の共通点」
- 「3分でわかるネクストギアの営業設計」
- 「導入前の不安にすべて答えるQ&A」
動画は「潜在層の温度を上げる装置」として活用できます。
視聴後にLPに誘導し、資料ダウンロードや無料相談につなげましょう。
3-5. SNSとブログで「継続的な接点」をつくる
潜在層とは、すぐに接点が生まれるとは限りません。
だからこそ、SNS(LinkedIn/Xなど)やオウンドメディアの活用で“見続けてもらう関係”をつくることが大切です。
具体的な発信例:
- 施策に取り組んだ結果や学び(リアルな現場感)
- 顧客からの声や成果
- 自社の営業哲学、実践している改善ノウハウ
- 成果が出た事例の要点
単なる宣伝ではなく、「この会社、現場をよく見ているな」「本質を捉えている」と感じてもらえる発信が大事です。
3-6. 潜在層を想定した広告クリエイティブを設計する
潜在層向けの広告は、「課題認識が浅い」「商材名すら検索しない」状態です。
だからこそ、“気持ちに刺さるクリエイティブ”が求められます。
有効な切り口:
- 「提案しても“検討します”で終わる営業に、終止符を。」
- 「営業代行で失敗した社長の、共通点。」
- 「なぜ、アポが取れても契約にならないのか?」
こうした広告から、「軽いLP」や「教育コンテンツ」へ誘導し、広告で“売る”のではなく“集めて教育する”構造をつくることが重要です。
まとめ:潜在層獲得には「設計」と「一貫性」がすべて
潜在層に対して成果を出すには、以下の3つを押さえることが不可欠です:
- “いきなり売らない”設計(信頼が先、サービス紹介は後)
- “多段階の育成”プロセス(ステップメール/動画/SNS)
- “価値観を届ける一貫性”(発信内容、LP、提案内容がブレない)
この設計がしっかりしていれば、
「まだ課題に気づいていなかった人」が、3ヶ月後にはあなたの会社に資料請求をしている。
そんな流れを毎月安定的に生み出すことができるのです。
第4章|潜在層から顕在層へ──育成と信頼構築のステップ設計
BtoBマーケティングにおいて、潜在層からリードを獲得するだけでは不十分です。
真に成果を出すには、「どう顧客の温度を上げていくか」、つまり“潜在層→準顕在層→顕在層”へと意識を変化させていく設計が必要不可欠です。
この章では、実際にどうやって信頼関係を構築し、見込み客を「相談したくなる状態」まで導いていくか、そのステップを具体的に解説します。
4-1. 潜在層の“感情”に寄り添うことから始める
潜在層は、まだ課題が明確になっていません。
だからこそ、最初に届けるべきは「事実」よりも「感情」です。
たとえば、こういった声に共感してもらえる切り口が有効です。
- 「頑張って営業してるのに、結果が出ない…」
- 「広告費はかけてるのに、成果につながらない…」
- 「何が悪いのか分からないけど、売上が伸びない…」
✅ ポイント:顧客自身が言語化できていない“違和感”や“フラストレーション”を代弁すること。
「なんでうちの状況わかるの…?」と思わせた時点で、ファーストステップは成功です。
4-2. 自社の“視点”で問題を再定義する
共感で関心を引いたあとは、自社ならではの「なぜそれが起きているのか?」という視点の提供を行います。
ここで重要なのは、「解決策を押し付けない」ことです。
まずは、問題の“構造”を整理してあげることが信頼につながります。
例:
- 「営業代行が成果につながらないのは、“アポ取得”だけをゴールにしているから」
- 「商談で即決できないのは、営業の問題ではなく“事前設計の欠如”が原因」
- 「契約率が低いのは、信頼が“商談時”にしか構築されていないから」
この段階では、“サービス紹介”ではなく、“考え方の提供”が主役です。
あなたの会社の独自性は、「やり方」ではなく「見方」にあります。
4-3. 小さな成功体験・納得体験を積み重ねる
潜在層の信頼を得るには、段階的に「わかる」→「できる」→「やってみたい」と思わせていく設計が必要です。
たとえば次のような“育成コンテンツ”が効果的です。
教育段階におけるコンテンツ例:
| フェーズ | 内容 | フォーマット例 |
|---|---|---|
| 気づき | なぜ成果が出ないのか? | ブログ記事/マンガ資料/3分動画 |
| 納得 | 自社のどこが問題なのか? | チェックリスト/診断ツール/構造図解 |
| 共感 | 他社も同じ課題を抱えていた | 導入事例/ストーリー漫画/インタビュー動画 |
| 希望 | 解決できる可能性を感じる | 成果比較表/変化のシナリオ/体験会案内 |
このように、「すぐ相談」ではなく「自然と相談したくなる」導線を設計することが肝です。
4-4. 行動のハードルを下げる“中間CTA”を複数設置
多くのBtoB企業のLPやWebサイトは、いきなり「無料相談」「お問い合わせ」しかない構成です。
これは、潜在層にとってはハードルが高すぎます。
そこでおすすめなのが、“中間CTA(Call to Action)”の活用です。
有効な中間CTAの例:
- 無料PDFのダウンロード
- メルマガ登録
- LINEで情報を受け取る
- 5分でできる無料診断
- 成功事例集の請求
このように、「ちょっとだけ行動できる選択肢」を複数用意することで、
“いきなり顧客にはなれない”潜在層の動きを自然に導くことができます。
4-5. 商談に至るまでの「信頼の積み重ね」を可視化する
潜在層の育成では、相手が「何を見て、何に反応したか」を記録・管理することが極めて重要です。
たとえば以下のような情報をトラッキングしましょう。
- どの資料をDLしたか
- ステップメールをどこまで読んだか
- LINEでどのメッセージに反応したか
- どの事例ページを何分見たか
- セミナー参加履歴があるか
このような情報が蓄積されていれば、「この人はもう提案しても良いタイミングかどうか」が定量的に判断できます。
これは属人的な営業ではなく、再現性のある“構造化されたナーチャリング”を実現するために欠かせない視点です。
4-6. 最後は“個別対応”ではなく“世界観”で動いてもらう
ここまでステップ設計を丁寧に積み重ねてきたら、最後の決め手は「口説く」ことではありません。
むしろ、「この会社の世界観に入ってみたい」「このチームと一緒に進みたい」と感じてもらうことです。
- どんな信念でサービスを作っているか
- なぜ、目の前の顧客を支援しているのか
- どんな未来を目指しているのか
この“想いのレイヤー”が伝わることで、商談は“選ばれる場”に変わります。
ここまで到達できれば、「値引きしてくれたから選んだ」「とりあえず比較してみた」という浅い関係ではなく、
LTVの高い顧客が自然と集まる構造が完成するのです。
まとめ|信頼は、段階を経て「育てる」もの
潜在層は、最初から顕在化しているわけではありません。
情報提供 → 気づき → 納得 → 共感 → 信頼 → 相談という“心の変化の階段”を1段ずつ上ってもらう必要があります。
そしてそのためには、
✅ 「段階的なコンテンツの設計」
✅ 「行動しやすいCTAの設置」
✅ 「リストの一元管理と温度管理」
が必要です。
リードの数を追う時代から、リードの育て方で勝負する時代へ。
この意識の変化こそが、BtoBマーケティングにおいて持続的な成果を生む“構造化された成長”の鍵になります。
第5章|成果を出している企業に共通する成功事例と設計思想
「うちも同じようにやっているのに、なぜあの会社だけ成果が出るのか?」
BtoBのWebリード獲得において、同じような施策を打っていても“結果に大きな差が出る”ケースが多くあります。
その差は、偶然ではありません。
成果を出している企業には、共通する「構造」と「思想」があるのです。
この章では、実際に成果を上げている企業の特徴と、そこにある“考え方の設計”を具体的に紹介します。
5-1. 成果を出している企業は「売らずに信頼されている」
成果が出ている会社の共通点、それは「売らずに売れている」という状態をつくっていることです。
例えば、以下のような現象が起きています:
- ホワイトペーパーやセミナー資料をダウンロードしてきた企業から「ぜひ話を聞きたい」と連絡が来る
- メールマガジンを半年読み続けた企業が「もう他は検討していません」と言ってくる
- YouTubeで見て共感した担当者が「御社にお願いしたい」と商談に来る
これらはすべて、価値提供を通じて“勝手に温度が上がる構造”を設計している結果です。
5-2. 事例①:半年リードゼロ→初月で契約獲得した探偵フランチャイズ本部
ある探偵業界のフランチャイズ本部は、営業活動を6ヶ月行っても加盟ゼロという状況でした。
そこで、「探偵」という言葉を使わずに、「IT企業が運営する調査ビジネス」という視点に切り替え、以下のような潜在層向け構造を設計しました:
- 業界経験ゼロの人が知りたい“現場のリアル”をストーリー化して発信
- 「会社の次の柱を探す中小企業オーナー向け」にポジションを再設計
- ホワイトペーパー→ステップメール→無料個別相談という流れを設計
結果、初月で1件の加盟契約を獲得し、その後半年で年間目標を達成。
競合が「探偵経験者募集」「副業OK」などで集客している中、完全に違う切り口で“選ばれる構造”をつくった成功例です。
5-3. 事例②:弊社支援による美容機器卸売事業が、2年目で年商2.5億円を実現
弊社が支援した美容機器D2B(業務用美容機器の法人向け卸売)事業では、まったくのゼロから立ち上げて2年目で年商2.5億円を達成しました。
この成果は、商品力や営業力だけで成し得たものではなく、“構造化されたリード獲得と教育設計”によって成し遂げられたものです。
実施した主な施策は以下の通り:
- 「売れる美容機器の条件とは?」という教育型ホワイトペーパーを設計
- 美容室・サロンオーナーの“潜在課題”をテーマにしたSEO記事・動画コンテンツを定期配信
- LPでは“製品の機能”ではなく“導入後の集客成功事例”を前面に押し出し、導入イメージを強化
- メールアドレスだけで取得できる軽いLPを導入し、ステップメールで信頼を醸成
- 営業フェーズでは「プレゼン」ではなく「診断→改善提案」という流れを徹底
さらに、営業部門が“教育済みのリード”のみを商談対象とする体制を構築。
その結果、リード単価・商談化率・契約率すべてのKPIが向上し、事業が急拡大しました。
✅ この成功の鍵は、「商品が良い」ことではなく、
「売れる状態を事前に設計し、構造的にリードを育てていたこと」にあります。
価格競争をせずに、“選ばれる側”として営業が機能する。
その仕組みを整えたことが、2年で2.5億という成果を可能にしたのです。
5-4. 成果を出す企業は「思想を届けている」
マーケティングで成果を出す企業のもう一つの共通点は、思想を発信していることです。
単に「うちのサービスはこんな機能があります」ではなく、
- 「私たちは、営業活動の本質は“商談前に勝負が決まる設計”だと考えています」
- 「成果が出ない理由を営業のせいにしてはいけない。それは経営設計の問題です」
- 「売れる会社は、“選ばれる構造”を先につくっている」
というような、自社の信念・哲学をコンテンツで表現しているのです。
これにより、「価値観に共感した企業」だけが集まり、無理なく契約が決まり、継続率も高くなるという理想の流れが生まれています。
5-5. すべての施策は“事前設計”から始まっている
成果が出ている企業に共通するもう一つの要素は、「戦術ではなく構造」で動いていることです。
- コンテンツをどう作るか?
- LPで何を伝えるか?
- どこで信頼を構築し、どのタイミングで相談に誘導するか?
- どのようにCRM・MAで管理し、温度の高いリードだけを商談に上げるか?
このすべてが、「全体構造の設計」から逆算されています。
マーケティングは“個別施策の足し算”ではありません。
事前に設計された“流れ”があるかどうかで、成果の差は明確に表れるのです。
まとめ|成果が出る企業は「構造×思想」で動いている
ここまでの内容を整理すると、成果を出す企業には次の共通項があります:
✅ 売ろうとせず、価値提供と共感から始めている
✅ 自社の思想・構造を言語化し、発信している
✅ 潜在層を獲得し、教育・信頼を経て商談につなげている
✅ リード獲得の設計、育成の設計、商談化の設計が一気通貫でできている
✅ データ管理とタイミング判断を“構造”で行っている
第6章|構造化リード獲得を社内に導入するための手順
ここまで、Webリード獲得の成功企業に共通する構造や事例、考え方を解説してきました。
では実際に、自社で「構造化されたリード獲得」を導入しようとしたとき、どこから手を付ければよいのでしょうか?
この章では、再現性のある形で仕組みを導入し、社内に根付かせるための実践ステップを順を追って紹介します。
6-1. ゴールを「成約」から逆算して設計する
まず最初に行うべきは、「何のためにリードを獲得するのか?」というゴール設定です。
資料請求の数?無料相談の数?ではありません。
真のゴールは「契約(成約)」であり、さらに言えば「継続的に利益を生む関係」の構築です。
そのために、以下の問いを明確にしましょう:
- どんな属性のリードが、成約に繋がりやすいのか?
- どのような信頼の積み重ねがあれば契約しやすいのか?
- 契約までに必要な「温度の変化」は何段階あるのか?
- 商談前にどこまで教育しておけば、比較されずに選ばれるか?
このように、“成約から逆算した構造”を設計することが、最初の一歩です。
6-2. リードの“温度階層”を定義し、段階ごとの役割を設計する
構造化されたマーケティングでは、「すべてのリードを同じ扱いにしない」ことが鉄則です。
そこで重要なのが、リードの温度を段階で分類し、それぞれに必要なアクションを整理することです。
例:温度別のリード分類と対応策
| 温度 | 状態 | 対応する施策 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 潜在層 | 課題に気づいていない | 教育コンテンツ・広告・SNS | 共感と興味 |
| 準顕在層 | 自社の課題を認識し始めている | ホワイトペーパー・動画・ステップメール | 課題の言語化と納得 |
| 顕在層 | 解決策を探している | 成功事例・商談誘導 | 比較優位・提案 |
この分類に沿って、リードの獲得方法、育成プロセス、管理体制をそれぞれ設計していきます。
6-3. 「教育コンテンツ→接点→信頼」の流れを先につくる
見込み客がいきなり「導入を検討したい」となることはありません。
だからこそ、まだ買う気がない段階から“教育される流れ”を用意しておく必要があります。
実際の流れイメージ:
- 広告やSNS経由で、ブログ記事やYouTubeに触れる
- 記事内からホワイトペーパーや診断コンテンツをダウンロード
- メールやLINEで「あるあるの課題」や「他社の成功ストーリー」に触れる
- “比較検討”に入る前に、「この会社に聞いてみよう」と思わせる
この一連の流れを設計し、それぞれの接点に役割を持たせることで、「売り込まずに選ばれる」構造が生まれます。
6-4. 管理体制:リードを“見える化”し、次の一手を判断できる状態をつくる
構造を設計しても、リードの管理がバラバラでは仕組みは機能しません。
そのために必要なのが、CRMやMAツールを活用した一元管理とスコアリング設計です。
管理すべき主な要素:
- いつ、どのチャネルから流入したか?
- どの資料をダウンロードしたか?
- どの動画・記事を見たか?
- ステップメールをどこまで読んでいるか?
- 商談を提案して良い“温度”にあるか?
こうしたデータを基に、「このリードはまだ育成段階」「この人には提案して良い」という判断を、営業担当でなくてもできる状態にしておくことが理想です。
6-5. 営業・マーケティングを一体で回すチーム体制を整える
多くのBtoB企業で見られる問題が、「マーケがリードを獲っても営業がフォローしない(できない)」という分断です。
これを防ぐには、マーケティングと営業を“同じKPI”で連動させることが大切です。
よくある誤解:
- マーケ「資料請求はたくさん来てます」
- 営業「でも、全然アポにならないです」
→ 構造が断絶している状態
解決の鍵:
- 成約から逆算した“見込み度”の基準を明文化
- 一緒にコンテンツ設計・ステップ設計を行う
- MAのデータを元に“優先対応リード”を可視化して営業と共有
このように、「一気通貫の構造」を営業とマーケで共に理解・運用する体制を作ることが重要です。
6-6. スタート時は“軽いリード獲得”から始めてテストを繰り返す
すべてを完璧に構築しようとすると、時間もリソースも膨大になります。
そこでおすすめなのが、まずは“軽いリード獲得→教育→信頼構築”の一連の流れを小さくつくって回すことです。
スモールスタートの例:
- 軽いLPを1本作成(メールアドレスのみ取得)
- 教育型ホワイトペーパーを1本作成
- ステップメール5通だけ作って登録者に送信
- 商談につながった人の声をもとに改善
こうすることで、「どこで温度が上がるのか?」「何が刺さったのか?」を実データで検証でき、次の改善に活かすことができます。
まとめ|構造は一気に完成させず、「回しながら強化する」
構造化されたリード獲得の仕組みは、一気に完成させるものではなく、“回しながら育てる”ものです。
- まずは「小さく始める」
- データを取りながら「温度の上がり方」を分析する
- 「勝ちパターン」が見えてきたら拡張・仕組み化
このサイクルを丁寧に回すことで、広告費に依存せず、営業リソースに悩まされず、**“信頼が資産化される仕組み”**が社内に根付きます。
第7章|広告・SEO・SNS…チャネル別!潜在層獲得の実践戦略
これまでの章で解説してきた通り、Webリード獲得で成果を出すためには、
「顕在層だけを狙うのではなく、潜在層を育てていく構造を持つこと」が重要です。
そのうえで、「どのチャネルでどう潜在層にアプローチしていくのか?」を考えることが、実行フェーズのカギになります。
この章では、代表的なチャネル別に“潜在層攻略の実践ポイント”を整理します。
7-1. 広告(Meta広告・YouTube広告)|最も速く潜在層と出会える手段
広告は、設計さえ正しければ最短で潜在層にリーチできる強力なチャネルです。
ただし、見込み客の“温度”に合わせて設計しなければ、費用だけが消化されて終わります。
潜在層広告の設計ポイント:
- 感情や日常の“違和感”に訴える
例:「営業しても“検討します”で終わる…に、終止符を。」 - 課題を明確にせず、共感と気づきを与える
例:「なぜ売れないのか分からない社長へ」 - 最初の接点は“軽いLP”または動画/記事
有効な広告チャネル:
- Meta広告(Instagram・Facebook):感情・共感訴求に強く、潜在層に届きやすい
- YouTube広告:3〜5分の教育動画を“気になるタイトル”でリーチできる
- Googleディスプレイ広告:リターゲティング用として活用
7-2. SEO(検索エンジン最適化)|“育成型の流入”を積み上げる資産
SEOは即効性こそないものの、中長期的な安定流入の基盤として欠かせません。
潜在層を意識した記事設計をすることで、検索経由で“悩み始めた人”を獲得できます。
潜在層向けキーワード例:
- 「営業 成果が出ない 原因」
- 「新規事業 売れない 理由」
- 「営業代行 成果 出ない 失敗」
コンテンツ設計のポイント:
- 商品名を出さず、課題の共感から始める
- 記事下で「もっと詳しく知りたい方はこちら」とホワイトペーパーやLINE登録へ導線
- 読了後のステップメールで教育設計
SEOは、“顕在化する前の検索”に入り込むことで、最初の信頼構築チャネルになり得ます。
7-3. SNS(X・LinkedIn)|価値観を伝える“関係資産”づくりに有効
SNSは、潜在層との間に“日常的な関係性”を築けるチャネルです。
特に社長や責任者自身が発信することで、企業の思想や現場のリアルが伝わり、見込み客の信頼を勝ち取ることができます。
SNS活用のポイント:
- ノウハウ投稿:教育・啓蒙になる短文知見(例:「成果の出ない営業チームの3大特徴」)
- 思想投稿:考え方・美学・価値観(例:「売る力ではなく、“選ばれる構造”こそ営業戦略」)
- 実践投稿:プロジェクト進行中の裏話・成果・失敗談などリアリティのあるもの
SNSはリードの“事前教育チャネル”として使えるため、LP流入や資料DLの成約率にも好影響をもたらします。
7-4. YouTube/動画|“共感と信頼”を一気に築くチャネル
テキストや画像では伝わりづらい「温度感」「人間性」「現場感」は、動画であれば一瞬で伝わります。
YouTubeで効果的なコンテンツ:
- 「◯◯の現場でよくある営業課題ベスト3」
- 「売上が上がらない原因は“商品”ではなく“構造”だった」
- 「実際に成果が出た事例解説」
また、動画→LINE誘導→ステップ配信という流れも強力です。
潜在層に向けた“顔が見える発信”は、見込み客を一気に前のめりにさせる武器になります。
7-5. LINE公式アカウント|“継続接点”としての最強メディア
近年、BtoBでもLINE活用が一般的になってきました。
メールよりも開封率が高く、個別対応にも強いため、潜在層との“1対1関係”のような安心感を提供できます。
活用例:
- 資料DLや動画視聴後にLINEで接続
- ステップ配信で、教育→共感→相談導線を作成
- 質問やリアクションを通じて見込み客の状態を可視化
LINEは「メールを見ない層」「まだ相談する気はない層」との接点維持にも効果的です。
7-6. どのチャネルを選ぶべきか?の判断基準
「結局、どのチャネルをやればいいの?」という問いに対しては、以下の観点で判断しましょう。
✅ 今すぐリードが欲しい → 広告(Meta・YouTube)
- ただし「教育→信頼」までの設計がセットで必要
✅ 安定した流入を作りたい → SEO+SNS
- 蓄積型の資産として、数ヶ月後に効き始める
✅ 顔が見える関係を作りたい → 動画・YouTube
- 潜在層の信頼構築・ファン化に効果大
✅ 継続的に接点を維持したい → LINE・ステップ配信
- 一度つながったリードを温め、商談へ引き上げる仕組みを構築可能
まとめ|チャネルは“点”ではなく“線”で設計する
もっとも重要なのは、単独のチャネルに依存しないことです。
各チャネルは単体で完結させるのではなく、一貫した流れの中で連動させる設計が成果の分かれ目になります。
たとえば:
- YouTube広告 → 軽いLPでLINE登録
- LINEでステップ教育 → 成功事例PDFダウンロード
- ステップメール → 無料相談誘導
- CRMで行動を可視化し、営業が接点を取る
これが「潜在層が勝手に温度を上げ、顕在化してくる」仕組みです。
チャネルは“通路”であり、通路の先に“信頼されるブランド”と“設計された導線”があることが成功の前提です。
第8章|まとめと次に取るべき一手
ここまで、BtoB企業がWebで見込み客(リード)を獲得し、
潜在層から信頼関係を築いて成約につなげるための「構造」と「設計思想」を解説してきました。
最終章では、全体の要点を振り返りながら、今すぐ始められる最初のアクションを提示します。
8-1. 本記事の要点まとめ
🔹 なぜ今、潜在層を狙うべきなのか?
- 顕在層は競争が激しく、CPAが高騰している
- 潜在層はリード獲得単価が低く、共感ベースの信頼が築ける
- LTVが高く、契約後も長く続く関係をつくれる
🔹 構造的に成果を出している企業の共通点
- 「売らずに売れる」仕組みがある
- 価値観・思想・教育でファン化させている
- コンテンツ→信頼→成約までの導線を一気通貫で設計している
- 弊社が支援した美容機器事業も2年で年商2.5億円達成(実例あり)
🔹 実行ステップの重要性
- すべては「成約から逆算した設計」がスタート
- 潜在層の“温度感”に合わせた教育設計と段階的育成がカギ
- MA・CRMツールを活用して“管理と実行”をチームで回す仕組みが重要
🔹 チャネル活用は“線”で設計せよ
- 広告・SEO・SNS・LINE・YouTubeなど、各チャネルは点ではなく流れの一部
- 「接点→教育→信頼→商談化」までのシナリオ設計が成果を左右する
8-2. あなたの会社で「今すぐやるべき一手」は?
ここから先は、「設計されているか・いないか」で成約率も営業効率も大きく差がついていきます。
もしあなたの会社が、
- 「資料請求は取れるけど、全然商談にならない」
- 「広告費がかさむばかりで、契約に結びつかない」
- 「営業に任せきりで、温度管理も育成も曖昧」
という状態なら、まず着手すべきはこれです。
✅ 最初の一手:
“軽いLP”と“教育コンテンツ”をセットで作る
たとえば…
- メールアドレスだけでダウンロードできるホワイトペーパーLP
- ステップメール5通で信頼と理解を高める構成
- LINE登録導線とYouTubeでの顔出し情報発信
このセットだけでも、月に数件の“前のめりな商談”を生む仕組みは十分に作れます。
8-3. それでも一歩踏み出せないなら──
「いいのはわかったけど、社内でやるリソースがない」
「設計に自信がない」「何が正しいかわからない」
──もしそう思っているなら、私たちスペシャルワンがお手伝いできます。
私たちは、単なるコンサルでも制作会社でもありません。
「戦略設計から実行、契約獲得まで一貫して責任を持つ」営業・マーケティングの実行代行チームです。
✅ どこからでもご相談ください
- 現状のLPや広告、コンテンツの改善点を見てほしい
- 成果が出ていない原因を構造的に診断してほしい
- 小さく試してみたいけど、どんな仕組みにすべきか相談したい
そんな方は、まずは下記の無料相談フォームからお問い合わせください。
ご希望であれば、【軽いLPの構成案】や【ホワイトペーパーの企画設計】などもご提案可能です。
まとめ
構造を持った会社は、やがて「選ばれる会社」になります。
そして、選ばれる会社には、広告や営業に追われない“自走する集客の仕組み”が育ちます。
今の売上は、過去の構造の結果。
未来の売上は、今日からつくる構造で決まります。
さあ、今こそ、“売る前に売れている仕組み”をあなたの会社にも。