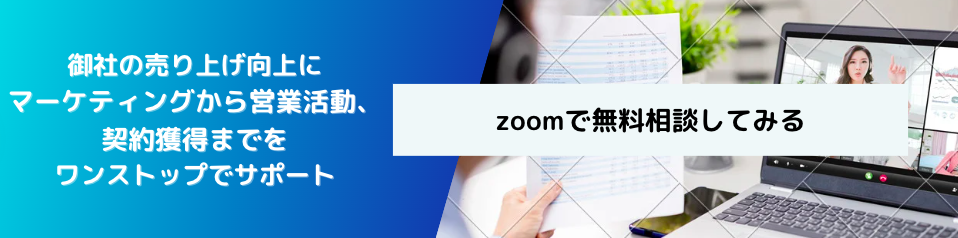新規事業を立ち上げたいけど、何から始めればいいか迷っていませんか?この記事では、中小企業が失敗しないための「新規事業」の開発フローを、フェーズごとにわかりやすく解説。段階的に進めることでリスクを抑え、着実に成果へとつなげるヒントが得られます。
第1章:そもそも「新規事業」とは何か?基本を解説
新規事業の定義と既存事業との違いとは?
「新規事業とは何か?」と問われた際、明確に答えられる企業は意外と少ないかもしれません。
新規事業とは、既存の市場や製品に依存せず、新たな価値を創出するビジネスの試みを指します。
たとえば、これまで製造業中心だった企業がITを活用してサービス領域に参入するケースなどが新規事業に該当します。
つまり、単なる延長線ではなく、「異なる顧客ニーズや市場セグメントを狙う活動」が含まれます。
一方、既存事業とは、現在すでに事業化されている製品やサービスのこと。
新規事業と既存事業の違いは、「収益構造が安定しているかどうか」と、「市場に対する知見の深さ」にあります。
既存事業は安定性がある反面、競合が多く差別化しにくいという課題もあります。
それに対し、新規事業は不確実性が高いですが、新しい収益機会を得るチャンスにもなり得ます。
これらを理解することが、新規事業フェーズを進める際の第一歩です。
事業拡大との違い/連携可能性
事業拡大と新規事業は混同されがちですが、本質的には異なります。
事業拡大は、既存サービスや製品の市場シェアを広げる取り組みです。
たとえば「販売エリアを拡大する」「オンライン販売を追加する」などが該当します。
つまり、既存のビジネスモデルをそのまま拡充・強化することが目的です。
対して、新規事業は新しい領域への挑戦です。
新たな顧客層や市場の開拓、まったく異なるビジネスモデルの構築が主な目的となります。
ただし、両者は連携させることで相乗効果を生むこともあります。
たとえば、既存事業で培ったノウハウや顧客データを活用し、新規事業の開発リスクを下げるといった戦略です。
このように、既存と新規を適切に分け、連携可能性を検討する視点が重要です。
新規事業に必要な考え方・成功のカギ
新規事業を成功させるには、従来とは異なるマインドセットと体制が求められます。
最大のポイントは、「仮説検証を前提とした柔軟な思考」を持つことです。
不確実性の高いフェーズでは、最初から完璧を求めるより、**小さく始めて学習を繰り返すこと(反復)**が有効です。
これは「リーンスタートアップ」などの考え方にも共通します。
また、成功には以下のような要素が不可欠です:
- 市場ニーズを的確に分析し、適切なターゲットを設定する力
- 社内外のリソース(人材・資金・情報)をバランスよく活用するスキル
- 各フェーズでの判断基準とKPIの明確化
- マーケティングと営業フェーズの早期設計と実行スピード
これらを可能にするためには、社内に限らず外部パートナーとの連携も視野に入れる必要があります。
特に、初期段階では限られた時間と人材で進めるケースが多いため、専門性のある支援会社との協力が成果を導く鍵となります。
第2章:新規事業の「7つのフェーズ」とは?全体像と成功のポイント
なぜフェーズ分けが重要なのか?
新規事業は、アイデアだけで成功するものではありません。
構想から収益化までの各ステップで、目的や課題は大きく異なります。
そのため、あらかじめフェーズを分けて整理することが成功のポイントです。
フェーズ分けによって「今、何をすべきか」「どの判断基準で進めるべきか」が明確になり、戦略的な意思決定が可能になります。
また、社内のリソース配分や外部支援のタイミングを検討する上でも、段階ごとの計画設計は非常に有効です。
これにより、失敗の確率を下げ、限られた予算や人材で効率よく進行できます。
企業の成長スピードが求められる今、フェーズを理解することは、リスク管理と同時に収益最大化の施策でもあります。
各フェーズの目的と進め方
新規事業を構築する際には、以下のような7つのフェーズが一般的です。
それぞれの段階で行うべきアクションと確認ポイントを整理しておくことが、継続的な進捗と改善を支えます。
以下に、各フェーズの概要と実施ポイントを解説します。
課題発見フェーズ
この段階では、どの市場・顧客層に向けた課題を解決するかを明確にします。
既存事業で得られた知見を活用しながら、新たなニーズや潜在的な問題を探ります。
このフェーズで重要なのは、市場調査とユーザーインタビューです。
競合他社の動向も含め、情報収集に時間をかけて進めるべきポイントです。
「なぜ今それをやるのか?」という問いに答えられるほど、課題の正確な定義が求められます。
解決すべき問題の重要度を誤ると、後の開発がすべて無駄になってしまいます。
アイデア創出フェーズ
課題が明確になったら、それを解決する製品やサービスのアイデアを生み出す段階です。
社内のブレインストーミングだけでなく、外部パートナーや専門家との共創も効果的です。
複数のアイデアを比較しながら、実現性・市場性・独自性の3つの視点で評価を行います。
このとき、仮説と検証のループを意識することが後のフェーズで役立ちます。
柔軟な発想と現実的な事業視点の両方を持つチーム体制が重要です。
コンセプト検証フェーズ
ここでは、選んだアイデアが本当に市場に受け入れられるかを小規模にテストするフェーズです。
ペルソナの設定やユーザー反応の仮測定など、定性的・定量的な評価手法を組み合わせて実施します。
顧客の声を反映しながら、プロトタイプを作成・修正し、価値提案を磨き上げていく作業が続きます。
ここでの学びを、次のMVP開発に活かすことが重要です。
MVP開発フェーズ
MVP(Minimum Viable Product)とは、必要最低限の機能を持つ製品・サービスの試作品です。
短期間で構築し、ユーザーからのフィードバックを得ることにフォーカスします。
この段階では、開発スピードとフィードバックループの速さが成功の鍵です。
時間をかけ過ぎると、ニーズや市場が変化してしまう恐れがあります。
MVPは社内チームで開発しても良いですが、開発コストや技術スキルが足りない場合は外部パートナーの活用も視野に入れましょう。
本格開発フェーズ
MVPで検証された価値提案をもとに、正式なプロダクト開発・サービス提供に移るフェーズです。
この段階からは、UI/UXの向上やマーケティング戦略の設計も同時並行で進める必要があります。
特に、リリース前には営業資料・LP・カスタマーサポート体制などの整備が求められます。
社内リソースが不足している場合は、外部のマーケティング支援会社の導入が成功率を高めます。
グロース(事業化)フェーズ
本格的にリリースされた後、顧客獲得と売上拡大を目的とするグロースフェーズに入ります。
KPIに基づいた広告運用・販促施策の実行が中心となり、ここで初めて「事業」として機能し始めます。
このフェーズでは、獲得コスト・LTV・継続率などの数値分析が不可欠です。
継続的なデータ収集と改善サイクルの運用体制を整えることで、事業の持続可能性が高まります。
収益化・組織定着フェーズ
売上が安定しはじめたら、事業の継続性を高め、組織の中に定着させる取り組みが必要です。
具体的には、人材採用・育成・運用体制の最適化、さらには新たな事業展開へのステップ設計が求められます。
収益が出ているからといって安心せず、常に課題を把握し、改善を継続する姿勢が重要です。
また、次の新規事業創出につなげるナレッジマネジメントや事後分析も、この段階で実施すると効果的です。
第3章:【フェーズごと】に見つかる課題とその乗り越え方
よくある失敗例と対処法
新規事業を進める中で、多くの企業が各フェーズで陥りがちな落とし穴に直面します。
特に中小企業では、限られた人材や予算の中で、スピード感と成果を同時に求められる環境が多く、計画通りに進めるのは容易ではありません。
以下は、実際に多く見られる失敗例と、その対処法です。
- 課題が曖昧なままスタート
→ 市場調査やユーザーインタビューを丁寧に行い、顧客の本質的なニーズを言語化する。 - 初期フェーズから開発に注力しすぎる
→ まずはMVPやプロトタイプでの検証を優先し、確度の高い仮説のみ進行する。 - マーケティング戦略が後回し
→ 「プロダクトが完成してから考える」では遅い。販売戦略やターゲット設定は初期から設計しておく。 - 社内の温度差や役割不明確でプロジェクト停滞
→ 最初に目的・目標・体制を明確にし、進捗管理体制(プロジェクトマネジメント)を構築することが必要。
これらの問題は、フェーズごとに適切なアクションをとることで回避・改善が可能です。
必須スキルと役割分担の考え方
新規事業の成功には、多様なスキルと明確な役割分担が求められます。
フェーズごとに求められるスキルは変化しますが、共通して重要なのが以下の3つです。
- 仮説検証力(問題を定義し、実験する力)
- コミュニケーション能力(社内外の連携を円滑にする)
- 実行力(限られたリソースの中で動かす力)
たとえば、課題発見フェーズではマーケティングリサーチや顧客インタビューが得意な人材が必要です。
一方、MVP開発フェーズでは開発ディレクションやUX設計のスキルが求められます。
さらに、社内で全てを補いきれない場合は、外部の専門家や支援会社をうまく活用する戦略も重要です。
それぞれの強みを活かした役割分担が、プロジェクトの推進力を高めます。
外部パートナーの活用が成功率を上げる理由
自社リソースだけで新規事業を進めようとするのは、時間と費用の両面で大きなリスクがあります。
特に広告運用やマーケティング分野では、専門知識がなければ無駄なコストがかかる可能性も高いです。
そのため、信頼できる外部パートナーと連携し、プロセスの一部を任せることが成功率を上げる要因になります。
株式会社スペシャルワンのような**「リード獲得から契約までをワンストップ支援する企業」**を活用することで、以下のようなメリットが得られます:
- 開発と同時にマーケティング施策を進められる
- 専門家がKPI設計やフェーズ管理を支援してくれる
- 短期間で結果を出す体制が整えられる
特に、フェーズが進むほど「売上を上げる体制づくり」が重要になるため、外部支援の活用は非常に効果的です。
フレームワーク例:リーンスタートアップ/PDCA/ビジネスモデルキャンバス
フェーズごとに見える課題に対応するには、フレームワークの活用が効果的です。
以下は特に有効とされる3つのフレームワークです。
リーンスタートアップ
「仮説 → 実験 → 学習」のループを高速で回す考え方です。
新規事業の不確実性を前提に、最小限の投資で顧客の反応を検証しながら改善を繰り返します。
PDCAサイクル
伝統的なマネジメント手法ですが、新規事業においてもフェーズ進行の中で有効に活用できます。
各フェーズで立てた計画(Plan)を確実に実行し(Do)、評価(Check)と改善(Action)をループさせることが重要です。
ビジネスモデルキャンバス
事業の全体像を9つの要素で整理できるツールです。
特に初期の構想段階や、社内共有に役立ちます。
収益構造・顧客層・チャネル・提供価値を俯瞰して見られる点が大きな特徴です。
これらのフレームワークをフェーズと組み合わせて活用することで、課題の見える化と論理的な判断が可能になります。
第4章:中小企業の現実:新規事業開発の“壁”と向き合う
現状認識とリソース不足というリアル
多くの中小企業では、「新規事業を立ち上げたい」という思いはあっても、実行に移す段階でつまずいてしまいます。
最も多い理由は、**「リソース不足」**です。
特に以下のような悩みが頻出です。
- 開発に必要な人材が社内にいない
- 日常業務が忙しく、新規事業に時間を割けない
- マーケティングや広告運用に詳しい社員がいない
- 社内に新しいことに挑戦する文化が根づいていない
これらの課題を放置すると、せっかくの事業アイデアも形になる前に立ち消えてしまいます。
フェーズが進むごとに、必要な専門性や判断力も増していきます。
リソースの見積もり不足や、役割分担の曖昧さが、新規事業開発における最大のボトルネックとなるのです。
自社内だけで完結しない時代
かつては、商品開発から販売までを自社完結型で進める企業が多くありました。
しかし今は、スピードと専門性が求められる時代です。
中小企業が限られたリソースで事業を成功させるには、外部の力を戦略的に取り入れる必要があります。
たとえば以下のような分野は、特に外部パートナーの活用が効果を発揮します。
- マーケティング戦略の設計と実行
- LP制作、広告運用、リード獲得
- ユーザー分析やCRM設計
- 営業支援や受注までのプロセス構築
これにより、社内の負荷を抑えながら専門性の高いアウトプットを生み出すことが可能になります。
特に、早期フェーズでの正しい方向性の見極めには、第三者の視点が有効です。
「広告・マーケティング」フェーズの重要性
新規事業の開発において、プロダクトやサービスが完成することだけでは成功とは言えません。
その後、どうやって顧客に届け、認知し、選ばれ、売上に転換していくかという「広告・マーケティング」フェーズが極めて重要です。
多くの企業が、「作ること」に注力するあまり、販売戦略や集客計画が後回しになってしまいます。
しかし、新規事業においてはこの部分こそが収益化・事業化の分かれ目となります。
広告の設計、ターゲティング、メディア選定、リード獲得導線…
これらは一つでもズレがあると、成果が出ないまま資金だけが消える可能性もあります。
そのため、広告やマーケティング戦略のプロと連携し、最初から事業化に向けた導線を敷くことが非常に有効です。
開発フェーズの後に来る「売上確保」の壁
MVPや正式リリースを経て、いよいよ市場に投入された段階で次に待っているのが、「売上確保」という新たなフェーズの壁です。
ここでは以下のような課題が顕在化します。
- リード数は取れても商談につながらない
- 商談は発生するが受注率が低い
- 顧客の解約率が高く、LTVが伸びない
- 顧客の声を反映する仕組みがない
つまり、プロダクト開発と並行して“売れる仕組み”を整えておくことが必要なのです。
このフェーズで多くの企業が気づくのが、**「プロダクトの良し悪しよりも、届け方と売り方が重要だった」**という事実。
逆に、ここを最初から設計していれば、早期の収益化と事業定着に成功する可能性が高まります。
第5章:新規事業を成功させるために「今すぐできること」5つ
新規事業に取り組みたいと思っても、
「どこから始めれば良いのかわからない」「準備不足で進められない」と感じる方は少なくありません。
ですが、いきなり大きなプロジェクトを動かす必要はありません。
まずは手元でできる“小さな整理”から始めることが、成功への第一歩です。
ここでは、今日からできる「新規事業を進めるための5つのアクション」をご紹介します。
1. 事業の現状を明文化する
まず最初に行いたいのは、自社の現状を客観的に把握することです。
- 既存事業でどのような売上構造になっているか
- 顧客層や市場の変化をどう捉えているか
- 事業の強み・弱みは何か?
このような情報をA4一枚程度で文章にしてみるだけでも、頭の中が整理され、
「どこに新たな価値を生み出せるのか」というヒントが見えてきます。
明文化によって、チーム間の認識ズレや意思決定のブレも減らすことができます。
2. 社内外の人材・スキルを整理する
新規事業には、多様なスキルとチーム構成が求められます。
- 開発スキル(システム・UI/UXなど)
- マーケティングスキル(広告・集客・分析)
- 営業・契約クロージング力
- プロジェクトマネジメント力
これらが社内にどの程度あるか、どこが不足しているかを整理することが重要です。
不足している部分は、外部のパートナーを検討するための判断材料にもなります。
社内に「何があって、何が足りないか」を見える化しましょう。
3. ビジネスモデルを言語化する
多くの企業がアイデアはあるが、事業モデルが整理できていない状態でスタートしてしまいます。
その結果、途中で開発が止まったり、営業導線がつくれずに失敗するケースも。
そこで役立つのが、ビジネスモデルキャンバスなどのフレームワークです。
- 顧客セグメント
- 提供価値
- チャネル
- 収益の構造
- コスト構造
これらを図や文章にして整理するだけで、事業全体の構造が明確になります。
メンバー間で共有しやすく、議論の質も高まります。
4. 外部パートナーの候補を探す
すべてを自社内で完結しようとする必要はありません。
むしろ、新規事業ほど**「スピード」と「専門性」が求められるため、外部の活用が前提**になる時代です。
- 広告運用の代行
- LP・クリエイティブ制作
- 営業支援・商談代行
- データ分析やCRM設計
どの工程で外部パートナーを入れるかを検討し、実績や相性で候補をピックアップしておくことで、
いざ動き出すタイミングでスムーズに進行できます。
5. 専門家に相談して進める戦略を立てる
「誰に相談すべきかわからない」という声も多く聞かれます。
そのような場合こそ、事業化まで見据えた実行支援ができる専門家に相談することが、成功への近道です。
- 仮説立てからMVP構築までをどう進めるか
- リード獲得や広告設計をどう始めるか
- 費用対効果の高い進め方はあるか?
これらの悩みを相談しながら、実際に手を動かしてくれるパートナーがいれば、スピードと成果が格段に変わります。
第6章:よくある質問(FAQ)まとめ
新規事業の立ち上げを検討している企業様から、日々多くのご相談をいただいています。
ここでは、特にご質問の多い内容をQ&A形式でご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。
- フェーズの期間はどれくらい?
-
事業の内容や市場の成熟度によって異なりますが、一般的に下記のような目安があります。
- 課題発見~アイデア創出:1〜2ヶ月
- コンセプト検証~MVP開発:2〜3ヶ月
- 本格開発〜グロースフェーズ:3〜6ヶ月
すべてを急ぐ必要はありませんが、1フェーズごとに目的と成果物を明確にすることが成功への近道です。
- すべて社内で対応すべき?
-
必ずしもすべてを社内で対応する必要はありません。
むしろ、新規事業はスピードと専門性が重要なため、必要な部分だけ外部パートナーを活用することが主流になっています。- 市場調査や広告設計 → 外部支援が効率的
- MVP開発や営業体制構築 → 内製化と併用が最適
- マーケティングが苦手な会社でも大丈夫?
-
はい、まったく問題ありません。
実際にご依頼いただく企業の多くは、広告やマーケティングの専門部署を持たない中小企業様です。スペシャルワンでは、以下をすべて代行・支援可能です:
- ターゲット選定/ペルソナ設計
- LP・広告クリエイティブの作成
- Google広告/SNS広告の運用
- 問い合わせ・リード管理の仕組みづくり
- 数値レポートと改善提案
「何がわからないのかも分からない」という状態からでも、ゼロから丁寧にサポートいたします。
- 具体的にどんなサポートをしてくれるの?
-
スペシャルワンがご提供するのは、新規事業のアイデア段階から「売上化」までを一気通貫で支援するサービスです。
主な支援内容は以下のとおりです:- 企画立案・事業戦略設計
- 市場調査・競合分析・ビジネスモデル構築
- LP制作・広告設計・SNS運用
- リード獲得・CRM導入・営業支援
- 商談資料作成・契約クロージング支援
- 成果レポートと改善提案の定期提供
「社内に新規事業担当がいない」「何から始めるかもわからない」という企業様でも、スペシャルワンが伴走型で支援します。
まとめ:新規事業は「フェーズごとの設計」が成功のカギ
中小企業が新規事業を成功させるためには、“思いつき”ではなく、“戦略と段階設計”による進行が欠かせません。
本記事では、企画から収益化までを7つのフェーズに分け、それぞれで見落としがちな課題・必要なスキル・成功のポイントを解説してきました。
特に、新規事業においては以下のような視点が重要です:
- 自社だけで完結せず、適切な外部パートナーと連携すること
- 開発後の「売るフェーズ」までを視野に入れたマーケティング設計
- リソースやスキルの整理を早期に行い、準備を段階的に進めること
そして、行動を後回しにせず、「今できる小さな一歩」から始めることが、将来の大きな成果につながります。
「何から始めていいかわからない」「自社でできるか不安」
そんな方のために、株式会社スペシャルワンでは無料相談を実施中です。
現状をヒアリングし、フェーズごとに必要な戦略や支援内容をご提案いたします。