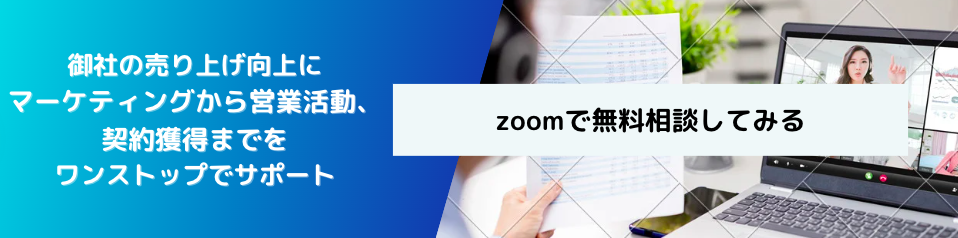カスタマージャーニーとは、顧客がサービスや商品に出会い、購入、継続利用に至るまでの一連の行動や感情の流れを可視化したものです。顧客理解が深まることで、マーケティング施策や営業活動の精度が格段に高まり、成果に直結します。本記事では、カスタマージャーニーマップの作り方から具体的な活用方法までを、実際の事例を交えてわかりやすく解説します。BtoBビジネスにおいて成果を出したい方は必見です。
カスタマージャーニーを作るメリット
カスタマージャーニーの可視化は、単なる「情報整理」にとどまりません。
それは、マーケティング施策全体の精度を引き上げる戦略設計の核ともいえる存在です。
以下では、カスタマージャーニーを作成・活用することで得られる代表的なメリットをご紹介します。
顧客理解が深まり、訴求精度が上がる
カスタマージャーニーを作成すると、顧客がどんな情報を求めているか、どのタイミングでどんな課題に直面しているかが明確になります。
それにより、下記のような改善が可能になります。
- 「お客様が本当に知りたいこと」に答えるコンテンツを設計できる
- 施策ごとにペルソナと目的を明確に区別できる
- 感情や心理面への訴求ができるようになる(例:「不安を払拭する」「期待を高める」)
たとえば、BtoBの新規事業立ち上げでは「導入後のサポートが不安」という声が多く、
それに合わせて「導入サポートの体制紹介」コンテンツを用意すれば、CV率の向上が期待できます。
施策の優先順位が明確になる
「どこから手を付けていいかわからない」といった悩みも、ジャーニーマップを作ることで整理されます。
ボトルネックが明確になり、改善ポイントが可視化されるためです。
例:
- 資料DL後に離脱が多い → コンテンツの質やステップ設計に問題があるかも
- サイトへの流入は多いが問い合わせが少ない → ページの訴求内容がずれている可能性
このように、データ×ジャーニー思考で施策を優先順位づけし、効率的にPDCAを回せます。
チーム間の連携がスムーズに
カスタマージャーニーは、マーケティング、営業、カスタマーサクセスなど複数部署の共通言語としても機能します。
- 施策の意図が明確になり、レビューやフィードバックもスムーズに
- 顧客との「接点」と「課題」をチームで共有
- 一貫性のある体験を提供しやすくなる
カスタマージャーニーマップの構成要素
カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)は、顧客の行動だけでなく、「誰が」「いつ」「どこで」「何を考え」「何に困っているか」までを体系的に整理したものです。
そのため、以下の4つの要素をきちんと設計することが、精度の高いマップづくりには欠かせません。
ペルソナ設定(誰に向けて設計するか)
マップを設計するうえで最も重要なのが、具体的なペルソナ(=理想的な顧客像)を設定することです。
- 業種、職種、役職(BtoBなら決裁者 or 実務者なども重要)
- 抱える課題やニーズ
- サービス導入を検討するきっかけ
たとえば、広告運用でリード獲得を狙う場合、「マーケティング担当者」と「営業責任者」では、関心のある情報が異なります。
この違いを整理しないと、刺さらない訴求になってしまう恐れがあります。
タッチポイント(接点)を洗い出す
顧客がどこでサービスと接点を持つのかを整理します。
この「タッチポイント」は、行動のきっかけや転換点となる重要な接触面です。
主なタッチポイントの例:
- 検索エンジン(SEO記事)
- SNS(広告、シェア投稿)
- 資料請求ページ、セミナー、展示会
- 比較サイト、口コミ、レビュー
それぞれの接点ごとに、顧客の心理状態や期待が異なるため、フェーズごとの適切な施策が必要になります。
顧客の行動・感情・課題を可視化
単に「行動」だけでなく、その時点の感情や課題、疑問、期待などの「心理面」も重要です。
例として、以下のような整理が有効です:
| フェーズ | 行動 | 感情・課題 |
|---|---|---|
| 認知 | 検索・広告を見る | 情報収集中、興味はあるが信頼できるか不安 |
| 比較・検討 | サイトを回遊、資料DL | 他社と比較して違いが分からない |
| 導入 | 問い合わせ・商談 | 効果が出るか確信が持てない |
これにより、どこで感情のハードルが発生しているか(離脱要因)を見つけることができます。
各ステージにおけるゴールを設定
それぞれのフェーズで、顧客が次に進むための「目的地」を明確にしておくことも大切です。
- 認知フェーズ:サービスの存在を知る → サイト訪問
- 比較フェーズ:他社との違いを理解する → 資料ダウンロード
- 契約フェーズ:不安を解消する → 問い合わせ or 商談化
このゴールを設計することで、的確なCTA(Call to Action)を配置でき、スムーズな購買行動を促進できます。
カスタマージャーニーマップの作り方【8ステップ】
カスタマージャーニーマップは、ただ感覚で作るものではありません。
戦略的に設計された8つのステップを踏むことで、実際のマーケティング・営業活動に活かせる強力なマップになります。
ここでは、マーケティング支援や広告運用で成果を上げるために効果的な8ステップをご紹介します。
ステップ① 目的の明確化
まずは、**なぜジャーニーマップを作るのか?**を明確にします。
- リード獲得数を増やしたい
- 資料請求から商談への移行率を上げたい
- 顧客接点ごとの課題を整理したい
目的があいまいだと、マップがただの図表になってしまいます。
**「このフェーズで何を改善したいのか」**という視点を持ちましょう。
ステップ② ペルソナの設定
ターゲットとなる**具体的な顧客像(ペルソナ)**を設計します。
- 企業規模・業種・担当者の役職
- 情報収集の手段(Web検索?SNS?)
- 抱える課題や悩み、導入の障壁
例:
BtoBサービスの場合、「導入を決める決裁者」と「比較検討を行う実務担当者」では重視するポイントが異なります。
複数ペルソナを想定するのも有効です。
ステップ③ タッチポイントの洗い出し
顧客が自社サービスと接触するあらゆる場面(=タッチポイント)をリストアップします。
- Web広告、SNS、展示会などの外部メディア
- 自社サイト、資料、ブログ記事などの自社資産
- オウンドメディアと営業資料の連携
これにより、どのチャネルでどんな情報提供が求められているかが見えてきます。
ステップ④ 顧客行動と感情の整理
ジャーニーマップの中核となるのが、フェーズごとの顧客行動・感情・ニーズの洗い出しです。
ここを丁寧に行うことで、どの段階で顧客がつまずくか、何を提供すべきかが明確になります。
具体的には、各フェーズで次の4つを整理します。
① 顧客行動(アクション)
- どんな行動をとるか?(例:検索する、資料を読む、比較サイトを見る)
② 顧客感情(エモーション)
- どんな気持ちでその行動をとるか?(例:期待、不安、疑問、焦り)
③ 顧客課題(ペインポイント)
- どんな壁や悩みを感じているか?(例:価格に納得できない、効果に不安)
④ 顧客ニーズ(インサイト)
どんな情報・体験を求めているか?(例:成功事例、導入後のサポート体制)
例えば、フェーズ別にまとめるとこのような形です。
| フェーズ | 顧客行動 | 顧客感情 | 顧客課題 | 顧客ニーズ |
|---|---|---|---|---|
| 認知 | SNS広告をクリック | 興味と警戒心 | 情報の信頼性に疑念 | 具体的な事例・導入実績 |
| 比較・検討 | 他社サイトと比較 | 期待と不安 | 違いがわかりにくい | サービスの強みと差別化 |
| 資料ダウンロード | 資料を読み込む | 導入の期待と懸念 | 成果保証への不安 | 導入効果や支援体制 |
| 問い合わせ | 質問フォーム送信 | 具体検討と慎重さ | 価格や運用負荷の懸念 | コスト効果・支援内容 |
こうすることで、単なる「行動の流れ」だけでなく、顧客心理に寄り添った設計ができ、
マーケティング施策や営業トークの精度が格段に上がります。
ステップ⑤ ボトルネックの発見
可視化されたジャーニーの中で、離脱が多い箇所や、行動が止まりやすい箇所=ボトルネックを見つけます。
- ページビューは多いが、資料請求が少ない
- 無料相談から契約までの転換率が低い
こうしたポイントは、コンテンツ改善・LP最適化・接客ツール導入などのヒントになります。
ステップ⑥ 解決施策・施策マッピング
見つけた課題に対して、何を・どこで・どう提供するかを整理します。
- 比較検討に悩む顧客には「導入事例」を提示
- 不安を感じる顧客には「FAQ」や「お客様の声」
このように感情や心理に寄り添った提案をマップ上に配置することで、自然なCV導線が作れます。
ステップ⑦ マップの可視化と共有
ここまで整理した情報を、1枚の図として見やすく可視化します。
- Excel、PowerPoint、Miro、Canvaなどのツールが便利
- フェーズごとの横軸と、感情や施策を縦軸に配置
社内の関係者と共通認識を持つツールとして活用することで、マーケ〜営業の連携も強化されます。
ステップ⑧ 定期的な見直し・改善
ジャーニーマップは一度作ったら終わりではなく、「育てる」ものです。
- 顧客ニーズや競合環境の変化
- 新しい施策の導入
- サービス改良
これらを反映することで、常に成果につながるマップとしてアップデートできます。
カスタマージャーニーマップの活用事例
カスタマージャーニーは「作って終わり」ではありません。
実際の施策に活用して成果に結びつけることが最も重要です。
ここでは、特に新規事業立ち上げ支援・広告運用・リード獲得といった文脈において、カスタマージャーニーマップをどう活用するかを事例ベースで解説します。
新規事業立ち上げ時の顧客導線設計
新規事業の立ち上げでは、市場ニーズの把握と正確なターゲット設定がカギを握ります。
事例:SaaS型ツール新規リリース支援の場合
- 【ペルソナ設定】
→ IT担当者、マーケティング責任者 - 【認知フェーズ施策】
→ 「課題整理」に役立つホワイトペーパーを提供 - 【比較検討フェーズ施策】
→ 無料トライアル導入事例をまとめた特設ページを設置 - 【契約フェーズ施策】
→ 初期導入サポート体制を紹介するウェビナー開催
このように、各フェーズに合わせたコンテンツやタッチポイントを設計することで、自然なリード育成と契約獲得が実現できました。
ポイント!
ジャーニーマップがあると、施策の「抜け漏れ」や「ズレ」を防げるため、
リリース初期からリード獲得効率を最大化できます。
広告運用と連動したリード獲得施策
広告運用においても、ジャーニーマップは極めて重要です。
クリック単価(CPC)だけでなく、CVR(コンバージョン率)を高める設計が可能になるためです。
事例:BtoB向けITソリューション広告運用
- 【広告クリエイティブ】
→ 認知フェーズに「課題共感型」のコピーを使用 - 【ランディングページ(LP)】
→ 比較検討フェーズ向けに、他社との比較表を掲載 - 【ダウンロード資料】
→ 「導入成果が出た5つの事例」など具体データを提示
広告を出すだけではなく、ターゲットの心理状態に合わせた情報提供を設計した結果、
CPCを抑えながらもリード単価(CPA)を30%以上削減できた実績があります。
ポイント!
広告配信先やクリエイティブだけでなく、クリック後の体験設計こそが勝敗を分けるという視点が重要です。
営業活動における顧客理解支援
営業部門でも、ジャーニーマップは非常に役立ちます。
事例:法人向けサービス営業の提案活動
- 営業担当者が、見込み顧客のフェーズを把握
(例:検討段階に入っている vs まだ認知段階) - フェーズに応じて提案資料や伝えるメッセージを最適化
- 顧客に寄り添った提案で、商談化率・契約率が向上
ポイント!
顧客がどの段階にいるかを把握していれば、
「押すべきか」「引くべきか」の判断が正確にでき、営業効率が飛躍的に上がります。
BtoBマーケティングにおけるジャーニー設計のコツ
BtoBマーケティングでは、BtoCと異なり購買プロセスが長く、関与する人物も多いため、
カスタマージャーニー設計にはより高度な視点が求められます。
ここでは、BtoBならではのジャーニー設計のコツを解説します。
複数関係者を意識したペルソナ設計
BtoBでは、ひとりの担当者だけで購買意思決定が完了するケースはほぼありません。
通常は、実務担当者・部門責任者・経営層など、複数の関係者が関わります。
だからこそ重要なのは:
- 担当者視点:「導入の手間」「運用のしやすさ」を重視
- 責任者視点:「ROI(投資対効果)」「リスク低減」を重視
- 経営層視点:「企業成長への貢献」「コストインパクト」を重視
各立場ごとにペルソナを設計し、それぞれに合わせた情報提供が不可欠です。
資料やコンテンツも「担当者向け」「決裁者向け」と作り分けると効果的です。
商談・契約ステージまでのプロセス設計
BtoBでは、リード獲得後の商談・契約までのプロセス設計が成否を左右します。
注意すべきポイントは:
- 初回接点後、すぐにクロージングを迫らない
- 中間地点で「比較検討を後押しするコンテンツ」を挟む
- 導入後の運用イメージを明確に示す資料を用意
例えば、資料請求後にすぐ「ご契約いかがですか?」と迫ると離脱される可能性が高いです。
まずは課題整理支援→事例紹介→無料相談といった段階的なアプローチが必要です。
このプロセス全体をジャーニーマップに落とし込み、顧客の心の動きに沿ってナーチャリングすることが成功のカギとなります。
ABM(アカウントベースドマーケティング)との併用
近年、BtoB領域では**ABM(Account Based Marketing)**という考え方も主流になっています。
ABMは、「特定のターゲット企業群に最適化した営業・マーケティング活動」を指しますが、
これとカスタマージャーニー設計は非常に相性が良いです。
具体的には:
- 優先ターゲット企業群ごとにジャーニーマップを作成
- 個社ごとの課題や導線設計をカスタマイズ
- マーケティングと営業が連携して個別攻略
このアプローチにより、受注率を飛躍的に高めることが可能になります。
カスタマージャーニー作成に使えるおすすめツール
カスタマージャーニーマップを手書きやExcelだけで作ろうとすると、どうしても情報整理が大変になります。
そこで便利なのが、視覚的に整理できる専用ツールの活用です。
ここでは、ジャーニーマップ作成に役立つツールをご紹介します。
Canva・Miroなどの可視化ツール
まずおすすめなのが、ビジュアルマップ作成に強いツールです。
Canva(キャンバ)
- 無料でも使えるデザインツール
- 「カスタマージャーニーマップ テンプレート」が豊富
- ドラッグ&ドロップで直感的に編集できる
Miro(ミロ)
- オンラインホワイトボードツール
- チームで同時編集・リアルタイム共有が可能
- フローチャート、マインドマップ形式にも対応
これらを使えば、顧客の行動・感情・タッチポイントを1枚の図に整理しやすくなり、
社内共有やプロジェクト進行もスムーズになります。
ポイント!
特に新規事業やマーケティングチームでは、ビジュアルのわかりやすさが成功のカギです。
HubSpot、SalesforceなどのCRM/MA連携ツール
次に、顧客データと連携できるCRM/MA(マーケティングオートメーション)ツールも強力な武器です。
HubSpot
- 無料から使えるオールインワン型CRM
- 顧客の行動履歴(メール開封、サイト訪問など)を自動追跡
- ジャーニーマップのアップデートに必要なデータ取得が容易
Salesforce
- 世界トップシェアのCRMプラットフォーム
- 大企業向けにスケーラブルな機能
- ABMやパーソナライズドナーチャリングに最適
これらを導入すれば、カスタマージャーニーを「仮説ベース」から「データベース」へ進化させることができます。
ポイント!
運用型広告、コンテンツマーケティング、営業支援すべてにデータドリブンな施策設計が可能になります。
まとめ|成果につながるカスタマージャーニー戦略とは
カスタマージャーニーマップは、単なる「図を作る作業」ではありません。
顧客視点に立ち、課題と期待を読み取り、最適な体験設計をするための戦略ツールです。
ここまでご紹介してきたように、ジャーニーマップを適切に設計・活用することで、
リード獲得から契約獲得、さらには顧客ロイヤルティ向上まで一貫して成果を最大化することが可能になります。
特に、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
顧客の「感情」まで設計してこそCVが伸びる
顧客は合理的にだけでなく、感情的に意思決定を行っています。
- 不安をどう解消するか
- ワクワク感をどう演出するか
- 疑念をどう払拭するか
このような心理プロセスを意識した設計こそ、CVR(コンバージョン率)向上の決め手です。
ただ情報を並べるだけではなく、顧客の心を動かす体験を設計しましょう。
プロによるサポートでスピードと質を両立
カスタマージャーニーマップの設計から施策実行までを自社だけで行うのは、
リソース的にも専門性の面でも負荷が大きいことが多いです。
そこで、マーケティング支援や広告運用のプロフェッショナルと連携することで、
- 設計スピードを飛躍的に高め
- 精度の高い仮説立案・検証を回し
- 実運用で成果を出す
という、質とスピードを兼ね備えたマーケティング実行が可能になります。