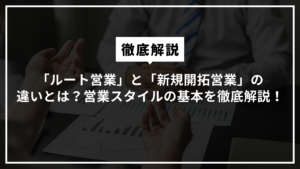BtoB営業を強化することで、見込み客を自ら獲得し、受注の仕組みを作ることが可能です。中小メーカーでも実践できる新規開拓の方法を、わかりやすく解説します。
はじめに
「うちは紹介だけで十分やってこれた」
そう感じている中小メーカーの経営者の方も少なくありません。
しかし近年、顧客ニーズの多様化や競合の増加により、従来の紹介頼みの営業だけでは、安定した受注や継続的な成長が難しくなっています。
本記事では、BtoB営業における新規開拓の重要性と、中小メーカーが直面する課題をわかりやすく解説します。
営業活動を見直し、新しい取引先を獲得したいと考える企業の方にとって、有益なヒントとなるはずです。
BtoB営業における新規開拓の重要性
BtoB営業とは、企業同士の取引を対象とした営業スタイルです。BtoC営業(個人向け)とは異なり、以下のような特徴があります。
・意思決定に複数人が関わる
・商談から契約までに時間がかかる
・一度の契約金額が大きい
・長期的な信頼関係が重視される
このような構造のため、新規顧客の開拓は企業の安定と成長に欠かせないものになります。
特に中小メーカーでは、既存顧客に売上が偏りやすいという傾向があります。
そのため、新規の法人顧客を増やすことには、次のようなメリットがあります。
・売上の柱を分散できる(リスクの軽減)
・顧客との力関係が安定する
・新しい市場や業界への展開が可能になる
・商品・サービス改善のヒントが得られる
・営業人材のスキルアップにつながる
既存のつながりだけに頼る営業体制は、紹介が止まった時点で成長も止まってしまう可能性があります。
今後を見据えるなら、自ら顧客を獲得できる仕組みづくりが必要です。
中小メーカーが直面する課題と現状
多くの中小企業が「新規開拓をやりたいが進められない」と感じています。
その背景には、いくつかの共通した課題があります。
1. 営業リソースの不足
営業を担当する人員が限られている中小メーカーでは、新しいアプローチにかける時間や人材が足りないという声が多くあります。
既存顧客の対応で手いっぱいになり、結果的に紹介頼みの体制から抜け出せない状況です。
2. 営業ノウハウの蓄積がない
BtoB営業における新規開拓には、ターゲットの明確化、ニーズの分析、アプローチ手法の設計など、専門的な知識と戦略的な実行力が求められます。
しかし、これらを社内で確立できている中小企業はまだ多くありません。
3. 顧客理解とニーズの把握が不十分
特に初めての業界や、新しい市場に進出する場合には、どの企業がどのような課題を抱えているかを把握することが非常に重要です。
顧客理解が浅いまま営業活動を進めると、時間や労力をかけても成果につながらないことがあります。
BtoB営業とBtoC営業の違いとは?
営業と一口に言っても、**BtoB(企業向け)とBtoC(個人向け)**では、営業のスタイルも求められるスキルも大きく異なります。
この違いを理解していないと、自社の営業戦略が的外れになってしまうこともあります。
ここでは、「取引先の特性と購買プロセスの違い」と「営業手法とアプローチの差異」に分けて解説します。
取引先の特性と購買プロセスの違い
BtoB営業は「企業を相手」に商品やサービスを提案する営業です。
一方、BtoC営業は「個人消費者」を対象に販売を行います。
そのため、取引先の性質や購入の流れには次のような違いがあります。
BtoB営業の特徴:
- 購買の決定に複数人が関わる(担当者・上司・決裁者など)
- 購買プロセスが論理的で、事業への効果が重視される
- 購入までに時間がかかる(資料請求→打合せ→稟議→契約)
- 長期的な取引を前提とすることが多い
- 契約単価が高く、導入後のサポートが重視される
BtoC営業の特徴:
- 購入を決めるのは本人のみ
- 感情やブランドイメージなど感覚的な要素も重視される
- 決断までの時間が短く、衝動買いもある
- 一度きりの購入も多く、関係が継続しにくい
- 契約単価は比較的低め
このように、BtoB営業では顧客のビジネス課題に対する理解が不可欠であり、提案型営業の力が求められます。
営業手法とアプローチの差異
営業のやり方にも、BtoBとBtoCでは明確な差があります。
どちらも「商品を売る」という目的は同じですが、そこに至るまでの流れや接点の作り方が異なります。
BtoB営業の主な手法:
- 訪問営業(フィールドセールス)
- インサイドセールス(非対面営業)
- メールマーケティング・資料送付
- オンライン商談・SFAツールの活用
- Web広告によるリード獲得
- 展示会・業界イベントへの出展
BtoC営業の主な手法:
- 店舗接客・販売員による対応
- テレビ・チラシなどのマス広告
- ECサイト・SNS・インフルエンサーによる集客
- キャンペーンやセールでの購買促進
BtoB営業では、顧客企業のニーズを深くヒアリングし、具体的な課題解決につながる提案をする力が重要です。
そのため、単純な商品の説明ではなく、**「この会社と取引するメリットは何か」**を相手に納得してもらう必要があります。
BtoCと比べて「説得力」や「根拠」を持った営業が求められる分、スキルや経験の差が成果に直結しやすいのが特徴です。
新規開拓営業のメリットとデメリット
既存の顧客だけで事業が回っているように見えても、中小メーカーにとって「新規開拓」は避けては通れないテーマです。
一方で、営業活動の負担が大きいという印象も強く、踏み出せない企業が多いのも事実です。
ここでは、新規開拓営業のメリットとデメリットを明確にし、検討の判断材料として活用できるように整理します。
新規開拓による売上向上と市場拡大の可能性
新規顧客の獲得には、以下のような大きなメリットがあります。
1. 売上の増加につながる
新しい取引先が増えることで、単純に売上の総量が増加します。特に、現在の売上が限られた顧客に偏っている企業では、収益の柱を複数持てるようになるため、経営の安定性が向上します。
2. 市場の拡大が実現できる
今までアプローチできていなかった業界やエリアにも営業をかけることで、自社の製品やサービスのニーズを新たに見つけることができます。これにより、事業のスケールアップやブランディングにもつながります。
3. 既存顧客とのバランスが取れる
新規顧客が増えることで、特定の顧客への依存度が下がり、営業交渉力や価格決定権のバランスも改善されます。
これは、営業担当者のモチベーションや自社の立場にも良い影響を与えます。
4. 営業スキルや組織力が鍛えられる
常に新しい顧客に対応するには、提案力・課題発見力・コミュニケーション能力など、営業スキルの底上げが必要になります。
組織としても、PDCAを回す体制や情報共有の仕組みが整い、長期的な人材育成にもつながります。
新規開拓に伴うリソース負担とリスク
一方で、新規開拓には明確なデメリットやリスクも存在します。
1. 工数と時間がかかる
最初から信頼関係が築けている既存顧客と違い、新規顧客との取引開始には情報収集・提案準備・ヒアリング・提案書作成・商談といった多くのステップが必要です。
営業担当者の負担は大きく、成果が出るまでに時間がかかるケースも少なくありません。
2. 成果が不確実
多くの労力をかけても、成約に至らないこともあります。特に、ターゲットの選定やニーズの理解が不十分な場合、営業活動が空回りしてしまい、リソースを無駄にしてしまう恐れもあります。
3. コスト面の負担が発生する
広告出稿や営業代行の活用、展示会出展など、新規顧客獲得には一定のコストがかかります。
見返りが得られなかった場合、投資に見合わない結果に終わるリスクもあります。
4. 担当者のモチベーション低下につながることも
新規開拓は成果が出るまでに時間がかかるため、担当者が「成果が出ない」と感じて疲弊することもあります。
適切な目標設定や社内での支援体制がないと、離職リスクにもつながりかねません。
成功するBtoB営業の特徴とは?
BtoB営業は「売る」ことだけが目的ではありません。
成功する営業には、顧客の理解力と関係性の構築力が求められます。
ここでは、成果を出すBtoB営業に共通する2つの重要な特徴について解説します。
効果的なターゲティングと顧客理解
BtoB営業では、「誰に何を売るか」を見誤ると、どれだけ営業活動を行っても成果にはつながりません。
そのため、まず重要になるのがターゲティングと顧客理解です。
効果的なターゲティングのポイント:
- 自社の強みや製品の特徴を整理する
- その強みが「どんな業種や業界のどんな課題に役立つのか」を明確にする
- 取引先候補をセグメント化し、優先順位をつけてアプローチする
このように、自社の商品が「誰にとって最適な解決策になるのか」を明確にした上で営業を行うことで、無駄な工数やアプローチのブレを防ぐことができます。
また、BtoBでは顧客企業の課題や業務フローを理解することが極めて重要です。
「なぜ困っているのか」「何が障壁になっているのか」といった、現場のリアルな課題感を把握するスキルが、提案の質を大きく左右します。
顧客理解が浅いまま営業を続けると、商品説明が中心になり、**「結局、うちにとって何のメリットがあるの?」**という疑問を解消できずに終わってしまいます。
営業の前に、業界の動向や担当者の立場、競合製品との違いなどをしっかりリサーチしておくことが成果への近道です。
信頼構築と長期的関係の重要性
BtoB営業では、商談成立後も関係が続く前提で営業する必要があります。
そのため、「売ったら終わり」ではなく、「売ってからが本番」という意識が欠かせません。
信頼構築の基本要素:
- 相手の課題に寄り添った提案ができているか
- 納期や対応など、基本的なビジネスマナーを守れているか
- 提案の裏にある論理やデータが納得できるものか
- 担当者個人だけでなく、企業対企業のつながりを意識しているか
一度信頼を得た企業とは、リピート率が高まり、契約単価が上がる傾向にあります。
さらに、満足度が高い顧客からは、別の企業を紹介してもらえる可能性も出てきます。
逆に、信頼を損なう対応をしてしまうと、その企業だけでなく同じ業界全体に悪い評判が広まることもあり得ます。
長期的な関係を築くには、短期的な売上だけに目を向けず、顧客の成長や成功に寄り添う姿勢が大切です。
中小メーカーが取り組むべき新規開拓のポイント
「新規開拓が大切なのは分かっているけれど、何から始めればいいか分からない」
そう感じている中小メーカーの経営者は少なくありません。
成功に近づくには、まず基本戦略の土台をしっかり作ることが大切です。
ここでは、その第一歩として取り組むべき2つのポイントをご紹介します。
自社の強みと差別化ポイントの明確化
営業活動を始める前に、まず取り組むべきなのが自社の強みの棚卸しです。
どんなに優れた製品やサービスを持っていても、それが他社とどう違うのか、誰のどんな課題を解決するのかが明確でなければ、顧客には響きません。
以下のような視点から、自社ならではの価値を整理しましょう。
・競合と比べて優れている機能や性能は何か
・導入後に顧客が得られる具体的な成果は何か
・自社にしかない技術や対応力があるか
・今までにどんな業界や顧客に評価されてきたか
こうした差別化のポイントを明確にすることで、営業先企業のニーズとマッチした時に、「それなら話を聞いてみたい」と思わせるきっかけをつくることができます。
さらに、社内でも営業メンバー全員がその強みを共有することで、一貫性のある提案やメッセージを届けやすくなります。
ターゲット市場と顧客ニーズの分析
自社の強みが整理できたら、次はそれを「誰に届けるのか」を明確にするフェーズです。
この部分が曖昧だと、せっかくの営業活動が広く浅くなり、成果が出にくくなります。
まずは、以下のような項目からターゲット市場を具体化してみましょう。
・業界(例:食品、自動車、IT、建設など)
・企業規模(従業員数や年商など)
・所在地(営業エリアや訪問可能地域)
・抱えている課題やニーズの傾向
たとえば「高精度の部品加工技術」が自社の強みなら、
「精密な部品を必要とする医療機器メーカー」や「自社で加工工程を持たない装置メーカー」など、具体的なニーズを持つ業界を狙うのが効果的です。
さらに、過去の商談データや既存顧客の傾向を分析することで、受注しやすい企業の特徴も見えてきます。
顧客のことを深く理解したうえでアプローチすることで、**「話が早い」「うちの課題を分かってくれている」**と感じてもらいやすくなり、商談が前向きに進みます。
効果的な新規開拓手法5選
「新規開拓」と聞くと、テレアポや飛び込み営業といった負担の大きい手法をイメージしがちですが、現代の営業活動にはもっと効率的で成果に直結しやすい方法が多く存在します。
ここでは、中小メーカーでも導入しやすく、実際に成果が上がっている5つの新規開拓手法をご紹介します。
1. デジタルマーケティングの活用
今やBtoB営業でもデジタル集客は当たり前の時代です。
見込み顧客は商談前にWeb検索やSNS、比較サイトなどで情報収集しているため、そこに露出できなければチャンスを逃してしまいます。
中小メーカーにとって効果的な施策は以下の通りです。
- 自社のホームページを営業ツール化(事例・導入効果・FAQの充実)
- リスティング広告・SNS広告で見込み顧客を集客
- ホワイトペーパーや資料請求を通じたリード獲得
少ない人員でも成果が出しやすく、自動化もしやすいのが強みです。
「営業の入り口」をつくる手段として非常に有効です。
2. 展示会や業界イベントへの参加
リアルな接点が生まれる場として、今も根強い効果があるのが展示会や業界の交流イベントです。
とくに製造業やBtoB業界では、顔の見える関係性が信頼に直結するため、名刺交換やブースでのやり取りが貴重なきっかけになります。
出展にはコストがかかるものの、
- 名刺獲得数が多い
- 業界関係者とのネットワークが広がる
- 競合や市場動向の調査もできる
といったメリットがあり、新規顧客の開拓だけでなく情報収集の場としても活用できます。
3. 既存顧客からの紹介制度の構築
「紹介で受注が続いている」という企業こそ、その紹介を仕組み化することで、新規開拓のスピードが大きく変わります。
例えば、
- 紹介してくれた企業への特典(割引やギフト)
- 顧客が紹介しやすくなるフォロー資料や実績紹介ページ
- 紹介しやすいタイミングでのお願い(導入後のフォロー時など)
などを整えることで、営業しなくても自然と顧客が増えていく体制を構築できます。
BtoB営業において、信頼の連鎖は非常に大きな武器になります。
4. 営業代行サービスの利用
「人手が足りないけど、新規開拓はしたい」という企業にとって、営業代行サービスの活用は非常に現実的な選択肢です。
営業代行を活用するメリット:
- プロの営業担当が商談機会を創出してくれる
- アポイント獲得からフォローまで一貫して対応可能
- 社内の営業リソースを本来の顧客対応に集中できる
特に、ターゲット選定やスクリプト設計、成果レポートまで任せられる代行会社を選ぶことで、社内にノウハウも蓄積されていきます。
スペシャルワンでは、広告運用から契約獲得までを一気通貫で支援しており、営業代行と連携することでより成果を出しやすい体制を整えています。
5. ソーシャルセリングとSNSの活用
営業=電話や訪問、というイメージは過去のものになりつつあります。
いま注目されているのが、SNSを活用したソーシャルセリングです。
特にLinkedInやX(旧Twitter)などを活用して、
- 業界関係者とつながり、情報発信を行う
- 専門性の高い投稿で「この会社、頼れそう」と思ってもらう
- 問い合わせのハードルを下げる
といった方法が取られています。
自社サイトに訪れる前から、企業や担当者の“中の人”として信頼を得ることが、新しい営業のカギになりつつあります。
新規開拓に成功した中小メーカーの事例紹介
「本当に成果が出るのか?」「うちでもできるのか?」
新規開拓に取り組もうと考えたとき、多くの企業が最初に抱く疑問です。
ここでは、実際に中小メーカーが成果を出した3つの事例を紹介します。自社の営業改善のヒントとしてご活用ください。
デジタルマーケティングでリード獲得に成功した事例
業種:産業機械部品の製造メーカー(従業員30名)
以前は飛び込み営業と紹介が中心で、新規開拓はまったく進んでいなかったこの企業。
社内にマーケティング人材がいないため、広告運用とLP制作を外部に依頼し、Web集客をスタートしました。
具体的には、
- 自社の強みを打ち出した特設ページを開設
- BtoBに特化したリスティング広告を出稿
- 資料請求フォームを設置して見込み顧客を蓄積
この施策により、月10件以上のリード獲得に成功し、そのうち3件が半年以内に契約に至るという結果を出しました。
「営業が顧客を探しに行く」から「営業が問い合わせに対応する体制」へと大きく変わった好事例です。
展示会出展で大手企業との取引を実現した事例
業種:樹脂加工メーカー(従業員20名)
業界内では知る人ぞ知る技術を持っていたものの、なかなか新規の取引が広がらず、営業に課題を抱えていました。
そこで初めて出展したのが、同業界の専門展示会。
- 出展にあたり、ターゲット業界に絞った展示内容を設計
- 顧客事例・製品サンプル・導入効果の見える資料を用意
- ブースに来場した企業に対し、即座に営業担当がヒアリングとフォロー
結果として、その場で名刺を獲得した80社中、10社と具体的な商談へ進行。
最終的に、業界大手の製造業2社と契約を獲得し、今では継続取引にまで発展しています。
「展示会は出すだけじゃ意味がない」と言われますが、戦略的な準備と即時対応の重要性を体現した成功事例です。
営業代行を活用して新規市場を開拓した事例
業種:試験装置メーカー(従業員15名)
自社で営業をしていたものの、限られた人員では新しい業界にアプローチする余裕がないという課題がありました。
そこで活用したのが、BtoB専門の営業代行会社。
外部の営業チームに以下を委託しました。
- 新しい業界に対するアプローチリストの作成
- テレアポおよびメール営業によるアポ獲得
- 商談前のヒアリング内容の共有と提案資料の整備
営業代行会社が毎月レポートを共有し、社内でも改善を進めながら進行。
3か月後には新規業界の取引先3社と初回契約が決定し、そこからさらに紹介も生まれるなど、新しい市場への突破口となりました。
「人手が足りないから新規は無理」と思いがちな状況でも、外部パートナーを使えば突破できることを証明した好例です。
新規開拓営業における注意点と対策
新規開拓は、取り組めばすぐ成果が出るというものではありません。
BtoB営業特有の「時間がかかる・関係が構築されていない・競合が多い」といった難しさをどう乗り越えるかが成功のカギです。
ここでは、よくある3つの壁とその対応策を整理してお伝えします。
リードタイムの長期化への対応策
BtoB営業の新規開拓では、受注までの期間が長くなりやすいという特徴があります。
理由は以下の通りです。
- 社内での検討・稟議に時間がかかる
- 複数部門の合意が必要
- 初回取引に慎重になる傾向がある
こうした「決断までの時間」に対応するには、**リード育成(ナーチャリング)**が重要です。
具体的な対策としては:
- 資料請求や問い合わせ後に継続的なフォローアップを行う
- 定期的なメールやニュースレターで自社の価値を伝え続ける
- Web上に事例紹介や導入メリットの分かるコンテンツを用意しておく
- 短期ではなく「半年後、1年後の契約」を見据えて関係を構築する
時間はかかりますが、信頼を積み上げることで受注率も高くなるのがBtoB営業の特徴です。
決裁者へのアプローチ方法
営業担当者と話が進んでも、最終的に決めるのは「決裁者」。
ここを押さえていないと、社内で提案が止まってしまうことが少なくありません。
そこで有効なアプローチ方法は以下の通りです。
- 初期段階から「御社ではどういう流れで導入が決まりますか?」と確認しておく
- 担当者との信頼関係を築き、「決裁者に伝えるための情報」を一緒に整理する
- 上層部向けに要点を絞った1枚資料やサマリー提案書を用意する
- 商談に同席してもらうチャンスがあれば、事前準備を万全にし、限られた時間で要点を伝える
重要なのは、**「担当者を味方にすること」と「決裁者の意思決定を手助けする提案をすること」**です。
競合との差別化戦略
「いい提案だったけど、今回は他社に決まりました」
このように、最終段階で競合に負けてしまうケースも新規開拓ではよくあります。
差別化で意識すべきポイントは、価格や機能の比較ではない軸で自社を伝えることです。
- 顧客の課題にどれだけ深く向き合っているか
- 提案内容がどれだけ「相手に合わせたもの」になっているか
- 導入後のサポートや対応体制に安心感があるか
- 他社事例や実績に基づいた「成功の再現性」があるか
特に中小メーカーの場合、大手とは違う柔軟性や親身さ、スピード感などが強みになります。
これを具体的に伝えられれば、価格競争ではない選ばれ方ができるようになります。
営業代行サービスを活用するメリットとは?
「新規開拓をしたいけど、社内にリソースがない」
「営業は苦手だけど、自社の製品には自信がある」
そんな中小メーカーにとって、営業代行サービスの活用は有効な選択肢です。
ここでは、営業代行の導入によって得られる具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。
リソース不足の解消と専門知識の活用
多くの中小企業では、営業を専門とする人材が社内に少なく、新規開拓を兼任できる人がいないという声が非常に多く聞かれます。
営業代行を活用することで、
- 営業活動の「立ち上げ」を外部に任せられる
- 見込み客のリスト作成や初期アプローチを効率化できる
- 自社では得られない営業ノウハウやトークスクリプトを活用できる
といった効果が期待できます。
さらに、ターゲット選定や競合分析の視点を持ったプロフェッショナルが対応してくれるため、成果が出やすい層に絞った効率的な営業活動が実現できます。
コスト効率と成果の最大化
「人を雇うほどではないけれど、営業力は欲しい」
このような状況で営業代行を活用する最大のメリットは、人材採用よりもはるかに低コストで営業機能を補えるという点です。
- 社員1人を採用・育成するよりも、短期的に成果が出やすい
- 成果に応じた報酬体系を選べば、無駄な固定費がかからない
- 営業活動の途中経過や効果がレポートされ、改善に役立つデータも得られる
営業代行会社は、複数の業界や商材の営業経験を持っているため、スピーディーな実行と修正が可能です。
「まずは小さく始めて様子を見る」という導入も可能なため、リスクを抑えたチャレンジがしやすいのも魅力です。
弊社のサービス紹介
新規開拓に関して、「やらなきゃいけないのは分かっている。でも、どうやって始めればいいか分からない」という声を多くの中小企業様からいただいてきました。
そこで私たちスペシャルワンでは、広告運用からリード獲得、さらに契約獲得までをワンストップで支援するサービスをご提供しています。
広告運用からリード獲得、契約獲得までのワンストップサービス
私たちのサービスは、単なる営業代行や広告運用とは異なります。
「成果につながる仕組みを一貫して構築する」ことにフォーカスしています。
具体的な支援内容は以下の通りです。
- 自社の強みを引き出す訴求軸の整理・設計
- ターゲットに合わせた広告運用(Google、SNS等)
- LP(ランディングページ)や営業資料の作成
- お問い合わせ・資料請求からの見込み顧客の獲得
- インサイドセールスを活用したアポ獲得・商談化
- 必要に応じたクロージング支援・営業代行
これにより、「マーケティング→営業→契約」の流れをまるごと任せられるため、リソースが限られた中小メーカーでも無理なく新規開拓をスタートできます。
サービス導入の流れとサポート体制
サービス導入までの流れは、非常にシンプルです。
1. 無料相談・ヒアリング
現在の営業課題や目的を伺い、最適な施策の方向性をご提案します。
2. 施策のご提案・お見積り
業種・ターゲット・ご予算に応じて、最適なプランを設計します。もちろん、ご相談だけでも大歓迎です。
3. 施策の実行・改善
広告配信や営業活動をスタートし、成果データをもとに改善を繰り返します。専任担当が定期的にレポートを共有します。
4. 契約獲得・運用の継続
リードが受注につながるよう、営業フェーズの支援も含めて並走。自社内に営業ノウハウを残す支援も行います。
導入後も、専任の担当者が伴走しながら、データ分析・改善提案・運用サポートを継続的に行います。
「任せたら終わり」ではなく、「一緒に売上を作る」という姿勢で取り組んでいます。
まとめ
BtoB営業における新規開拓は、中小メーカーの成長と安定に欠かせない重要な取り組みです。
紹介や既存顧客に頼る営業体制だけでは、将来的な受注の減少や市場変化に対応できないリスクも高まります。
本記事では、新規開拓の重要性やBtoB営業との違い、具体的な成功手法や注意点、さらに営業代行などの外部サービス活用のポイントまで、幅広く解説しました。
とはいえ、実際に行動に移すとなると、
- どこから手をつけていいか分からない
- 営業や広告の知識がない
- 社内に任せられる人がいない
といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな時こそ、プロのサポートをうまく活用することが成功への近道です。
スペシャルワンでは、広告運用・営業代行・資料作成・契約支援まで、すべてを一括でお任せいただける体制を整えています。
貴社の強みを活かした新規開拓戦略を、私たちと一緒に実現しませんか?
まずはお気軽にご相談ください。無料のヒアリングからスタート可能です。