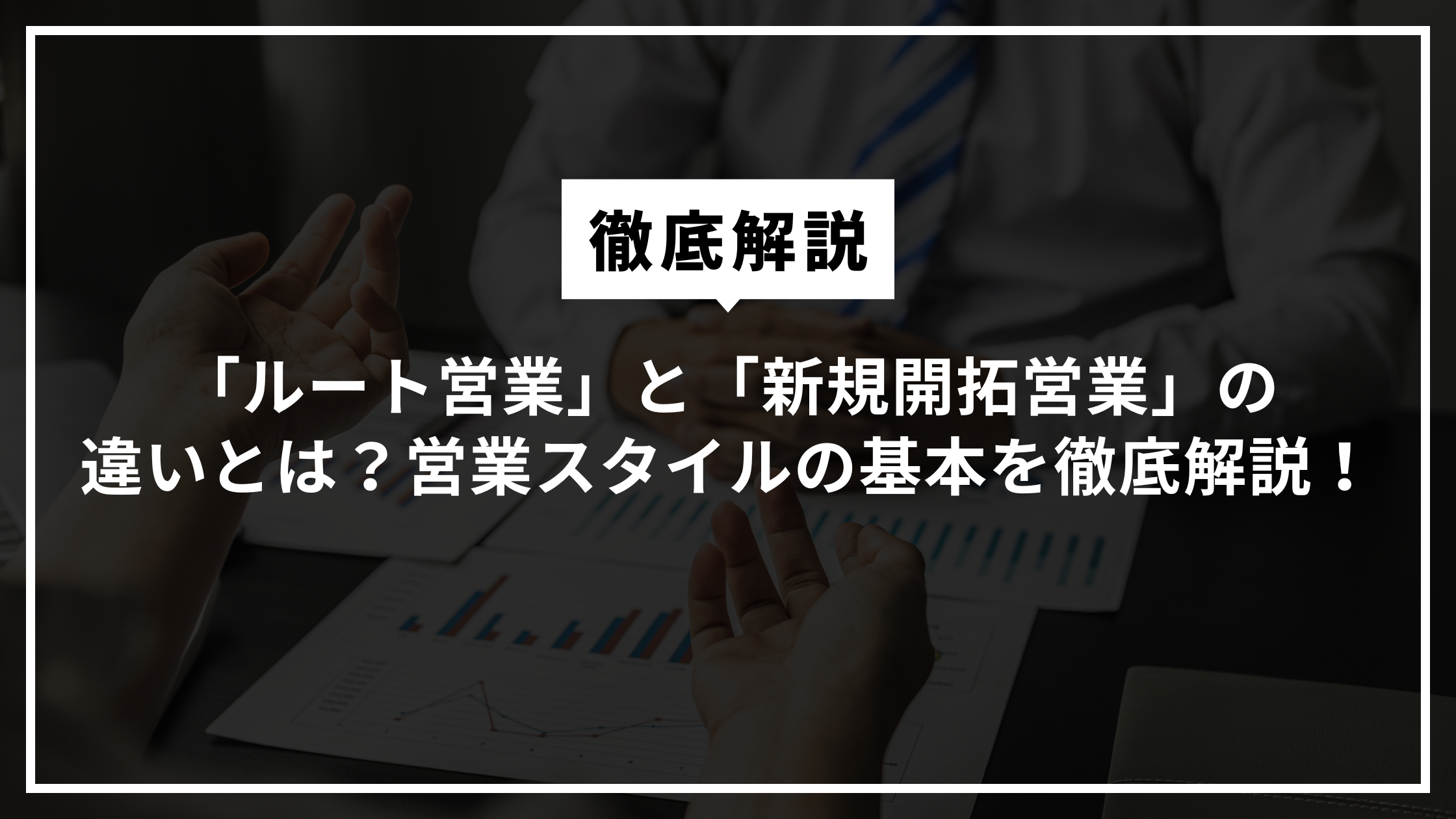「ルート営業と新規開拓営業、実際どちらが自社に向いているのかご存じですか?」
本記事では、それぞれの営業手法の違いを分かりやすく解説し、営業戦略に活かせるメリットを紹介します。新規開拓に悩む中小企業必見です!
営業とは何か?基本から押さえるビジネス戦略
営業は、企業が商品やサービスを顧客に提供し、売上を上げるための重要な活動です。
特にBtoB(企業間取引)においては、営業活動の質が企業の成長を左右します。
本記事では、営業の基本概念、目的と役割、BtoB営業で求められるスキル、
そして営業活動を成功させるための基礎知識と戦略について解説します。
営業の目的と役割とは
営業の主な目的は、顧客のニーズを満たす商品やサービスを提供し、
企業の売上と利益を向上させることです。具体的な役割としては以下の点が挙げられます。
顧客のニーズ把握
市場調査や直接的なヒアリングを通じて、顧客が求めるものを理解します。
商品・サービスの提案
顧客の課題や要望に応じて、最適な商品やサービスを紹介します。
信頼関係の構築
信頼を得るためのコミュニケーションや定期的な訪問を行い、継続的な取引を促進します。
アフターフォロー
購入後のサポートや追加提案を行い、顧客満足度を高めることができます。
BtoB営業で求められるスキルと成果の出し方
BtoB営業では、以下のスキルが特に重要とされています。
コミュニケーション能力
顧客との円滑なやり取りを通じて、信頼関係を築きます。
課題解決能力
顧客のビジネス課題を理解し、適切なソリューションを提供します。
商品知識
自社の商品やサービスに関する深い理解を持ち、的確な提案を行います。
時間管理能力
複数の顧客や案件を効率的に管理し、成果を最大化します。
営業活動を成功させるための基礎知識と戦略
営業活動を効果的に進めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
ターゲットの明確化
自社の商品やサービスが最も価値を提供できる顧客層を特定します。
情報収集
市場動向や競合他社の状況を把握し、戦略立案に活用します。
計画的なアプローチ
訪問計画や提案内容を事前に準備し、効率的な営業活動を行います。
フィードバックの活用
顧客からの意見や要望を収集し、商品やサービスの改善に役立てます。
これらの戦略を実践することで、営業活動の効果を高め、持続的な成果を上げることが可能となります。
ルート営業の特徴と業務内容を解説
ルート営業は、既存の取引先を定期的に訪問し、関係性を維持・強化する営業手法です。
新規開拓営業とは異なり、すでに取引のある顧客へのフォローや追加提案が主な業務となります。
ルートセールスの基本的な仕事内容とは
ルート営業の主な業務内容は以下のとおりです。
定期訪問
既存顧客を定期的に訪問し、商品の使用状況や満足度を確認します。
注文の確認
顧客の在庫状況を把握し、追加注文の必要性を確認します。
商品・サービスの提案
新商品や関連商品の紹介、既存商品のアップグレード提案を行います。
アフターフォロー
納品後のサポートや、トラブル対応を行い、顧客満足度を高めます。
これらの業務を通じて、顧客との信頼関係を築き、継続的な取引を促進します。
顧客との信頼関係を築くプロセス
信頼関係の構築は、ルート営業において最も重要な要素の一つです。
以下のプロセスが効果的です。
定期的なコミュニケーション
訪問や連絡を通じて、顧客の現状やニーズを把握します。
誠実な対応
問い合わせや要望に対し、迅速かつ誠実に対応します。
価値提供
顧客の課題解決に向けた具体的な提案や情報提供を行い、信頼を得ます。
これらを継続することで、顧客との信頼関係を深め、長期的な取引につながります。
安定した売上を生むメリットと注意点
メリット
- 安定した売上の確保:既存顧客との継続的な取引により、安定した売上が期待できます。
- 深い顧客理解:長期的な関係性を通じて、顧客のビジネスやニーズを深く理解できます。
注意点
- 新規開拓不足:既存顧客に注力しすぎると、新規顧客の開拓が疎かになるリスクがあります。
- マンネリ化のリスク:同じ業務の繰り返しで、新しい提案や工夫が不足しがちです。
これらの注意点を理解した上で、バランスよく営業活動を進めることが重要です。
成功事例に学ぶルート営業の活かし方
事例:定期的なフォローアップによる顧客満足度の向上
ある製造業の企業では、毎月定期的に顧客を訪問し、製品の使用状況や課題をヒアリング。
それに応じて即座に対応することで信頼関係を構築し、リピート注文の増加に成功しました。
このように、定期フォローと迅速対応はルート営業の成果を大きく左右します。
新規開拓営業とは?成果を上げるために知るべきこと
新規開拓営業は、これまで接点のなかった顧客にアプローチし、ゼロから関係を築き、契約に結びつける営業手法です。
既存顧客を相手にするルート営業と異なり、高い提案力・ヒアリング力・粘り強さが求められる難易度の高いスタイルですが、売上の伸びしろが大きく、企業の成長には欠かせません。
新規営業の役割と難易度
新規営業には主に以下のような役割があります。
市場の拡大
新しい業界やターゲット層に対して営業を行うことで、ビジネスチャンスを広げられます。
リスクの分散
既存顧客への依存を減らし、安定した売上基盤を構築できます。
潜在ニーズの発見
新規の顧客と接することで、これまで見えていなかった課題やニーズを発見できます。
一方で、以下のような難しさもあります。
- 顧客との信頼関係がゼロからのスタートであること
- 高いアポ取得・成約のハードル
- 断られることが多く、心理的な負担が大きい
- 継続的な行動と改善が必要
開拓でよくある失敗と成功パターン
よくある失敗
- 事前調査をせずに提案してしまう
- 顧客視点のない「押し売り型」営業
- フォローアップを怠り、関係性が切れる
- 競合との差別化が伝わらない
成功するパターン
- 顧客の課題に焦点をあてたアプローチ
- 初回接触からの関係構築を意識した営業フロー
- ニーズを深掘りするヒアリング力の発揮
- 顧客ごとに合わせた柔軟な提案と改善提案
このような成功パターンを営業チームで仕組み化することで、安定的な新規開拓が可能になります。
新規開拓の具体的な手法と営業フレームワーク
新規開拓営業で活用される代表的な手法には以下があります。
リスト営業(リスト作成+テレアポ)
対象企業を精査した上で、電話やメールで接触。ヒアリングと提案まで繋げます。
飛び込み営業
地域密着や業界特化型のサービスにおいて今でも効果的なアプローチです。
デジタルマーケティング連携
広告や資料ダウンロードで獲得したリードに対し、インサイドセールスを行う手法。
営業フレームワークの活用
BANT(予算・決裁者・ニーズ・導入時期)、FAB(特徴→利点→利益)などを使った構造的な提案が有効です。
テレマーケティングや交流会の活用ポイント
テレマーケティング
外注も含め、効率よく数を打てる手法。短時間でニーズ確認が可能ですが、断られるケースも多いため、質の高いトークスクリプトが必要です。
ビジネス交流会・展示会
ターゲット企業の決裁者と直接つながれる機会。名刺交換後のフォローアップが成果を分けます。
SNSやメディア露出
情報発信を通じて企業認知度を高め、アポなしでも興味を持ってもらえる状態をつくる「認知→信頼」戦略です。
ルート営業と新規開拓営業の違いとは?
営業にはさまざまなスタイルがありますが、特に「ルート営業」と「新規開拓営業」は、企業の営業戦略において基本かつ重要な二軸です。
このセクションでは、それぞれの違いを明確にし、自社に合った営業手法を選ぶヒントを解説します。
対象顧客の違い(既存 vs 潜在)
ルート営業は、すでに取引実績のある既存顧客を対象に、関係の維持・強化を目的とした営業スタイルです。
定期的な訪問やフォローを行いながら、アップセルやクロスセルによって売上を伸ばすことが可能です。
一方、新規開拓営業は、まだ接点のない潜在顧客に対してアプローチすることが主な目的です。
新しい市場や業界へ参入するきっかけとなり、将来の柱となる取引先を獲得できるチャンスがあります。
アプローチ手法とKPIの比較
ルート営業のアプローチとKPI
- 手法:定期訪問、アフターフォロー、定着サポート、アップセル提案
- KPI例:訪問回数、受注継続率、顧客満足度、顧客ごとの売上
新規開拓営業のアプローチとKPI
- 手法:テレアポ、メール営業、セミナー参加、展示会、SNSなどからのリード獲得
- KPI例:アポ取得率、商談化率、初回受注率、リード数
どちらの営業スタイルでも、「見込み顧客をどう増やすか」「どう成果につなげるか」が重要な視点になります。
管理・効率化のしやすさの違い
ルート営業はスケジュールや対応フローがルーティン化しやすく、SFAやCRMでの管理が効率的です。
顧客ごとの履歴や対応状況が蓄積されるため、担当者交代時もスムーズに引き継げます。
一方、新規開拓営業は状況が流動的で、ターゲット選定から戦略の微調整まで柔軟な対応が必要です。
その分、営業フローやトークスクリプトの設計、パイプライン管理が成果に大きく影響します。
目的に応じた営業手法の選び方
ルート営業が向いているケース
- 顧客との長期的な関係構築を重視したい
- 安定した売上を維持したい
- アフターサポートや商品提案を通じてLTVを高めたい
新規開拓営業が向いているケース
- 新市場・新業界への進出を狙っている
- 売上を拡大するための取引先を増やしたい
- 既存ルートに依存せず、新たな収益の柱をつくりたい
それぞれの営業には役割と強みがあり、どちらか一方に偏るのではなく、戦略的に両者を使い分けることが、今後の営業力強化のカギとなります。
それぞれのメリット・デメリットまとめ
営業活動において、「ルート営業」と「新規開拓営業」にはそれぞれ異なる強みと課題があります。
このセクションでは、両者のメリット・デメリットを比較し、どちらを重視すべきかの判断基準をまとめて解説します。
ルート営業のメリット・デメリット
メリット
- 安定した売上の確保
既存顧客との継続的な取引により、売上の予測が立てやすくなります。 - 計画的な業務管理
訪問スケジュールや営業内容が定型化されており、業務の管理がしやすいのが特徴です。 - 信頼関係の構築がしやすい
継続的な接点を持つことで、顧客の信頼を得やすく、アップセルやクロスセルにもつながります。 - 精神的ストレスが少ない
知らない顧客にアプローチする新規開拓と違い、対話のハードルが低く安心感があります。
デメリット
- 成長の伸びしろが限定的
既存顧客の予算やニーズには限界があるため、売上の大幅成長は難しい場合があります。 - 営業がマンネリ化しやすい
同じような業務が続くことで、提案力や改善意識が低下する恐れもあります。 - 新しい市場に弱い
既存ルートに依存しすぎると、市場の変化や競合に対して脆弱になる可能性があります。
新規開拓営業のメリット・デメリット
メリット
- 新しい市場へのチャレンジが可能
自社がまだ入っていない業界や地域へ参入することで、大きな成長を期待できます。 - 売上拡大のチャンスが多い
新しい顧客との取引開始によって、ビジネス規模が拡張しやすくなります。 - 競合との差別化を発揮しやすい
まだ接点のない企業に対して、自社の強みをアピールすることで優位性を築けます。
デメリット
- 成果までに時間がかかる
信頼構築からスタートするため、売上貢献までに一定の期間が必要です。 - 拒否率が高く、精神的負担が大きい
テレアポやメール営業で断られることも多く、メンタル面の強さが求められます。 - コストと労力がかかる
ターゲット選定から接触、商談、成約まで、人的リソースと時間を多く使います。
どちらを重視すべきか判断するポイント
以下の視点で、どちらの営業手法を強化すべきかを判断できます。
事業のステージ
- 安定重視・堅実成長を目指す企業:ルート営業に注力し、顧客との深い関係性を構築
- 攻めの姿勢・拡大戦略を狙う企業:新規開拓営業を強化し、新たな市場を開く
リソース配分
- 営業人員が限られている場合:既存顧客のフォローに集中し、LTV(顧客生涯価値)を上げる
- 人員に余裕がある、または外部支援が可能な場合:新規開拓チームの組成やアウトソーシング活用も視野に
売上の現状と目標
- 現在の売上が既存顧客から安定的に出ているなら、アップセル強化で効率化を
- 売上が頭打ちで、伸びしろを探しているなら、新規獲得ルートの設計を
営業活動の効率を上げるツールと管理術
営業活動の成果を最大化するためには、属人的なスキルだけでなく、ツールやシステムを活用した「効率化」が不可欠です。
この章では、SFAやCRMの基礎知識から、営業プロセスを可視化して改善するための具体策まで、実践的な営業管理の方法を解説します。
SFA・CRMの基礎とおすすめツール一覧
SFA(営業支援システム)とは
営業プロセスを自動化・効率化し、商談管理や売上予測を可能にするシステム。情報を一元化し、チーム全体の生産性を高めます。
CRM(顧客関係管理システム)とは
顧客情報・接触履歴・ニーズなどを一元管理し、関係構築をサポートするシステム。既存顧客との深い関係を継続的に維持するのに役立ちます。
おすすめツール例
- Salesforce Sales Cloud:高機能で業界トップのSFA/CRMツール。自由度と分析機能が非常に高い。
- GENIEE SFA/CRM:営業向けに特化した国産システム。現場に馴染みやすいUIが特徴。
- eセールスマネージャーRemix Cloud:日本の営業現場に最適化されたSFA。AI分析も搭載。
- Zoho CRM:中小企業向けでコスパが高い。多機能で連携の柔軟性も◎。
- kintone:アプリを自由に組める柔軟性が高く、営業管理にもカスタマイズ可能。
営業管理に強いクラウドシステム活用法
クラウド型営業支援システムを導入することで、以下のようなメリットが得られます:
- リアルタイム共有:チーム間で進捗状況や顧客情報を即時共有可能
- コスト削減:サーバー不要・初期投資少なめで始めやすい
- 柔軟な拡張性:事業規模に合わせて機能追加・ユーザー追加が可能
特に、テレワークやフィールド営業が混在する今の時代には、場所を問わない営業管理が可能なクラウドSFAは強力な武器となります。
KPI設定・分析・改善のフレームワーク
成果を上げる営業チームには、「見えるKPI」があります。以下のフレームで構築していきましょう。
- 目標設定:売上・案件数・リード数など、最終成果に直結する目標を明確にする
- 指標設定(KPI):アポ取得率、商談化率、成約率など、中間指標を明確に
- 分析と課題抽出:CRM/SFAデータから、ボトルネックや改善点を分析
- 改善アクション実行:課題に対して具体的な手段を設定し、PDCAをまわす
KPIは“測れるもの”からスタートするのがコツです。
営業プロセスの可視化で生産性を向上させる方法
営業活動は「感覚」ではなく「データ」で改善すべきです。プロセスの可視化によって:
- どこで機会損失が起きているかが分かる
- 属人化している業務を洗い出し、ナレッジ化できる
- 育成スピードの加速:新人にもプロセスが見えるので育てやすい
SFAの「ダッシュボード」機能を活用し、営業ステータス(初回接触・商談中・失注・受注など)を一目で確認できる状態にしましょう。
貴社の営業力を最大化するには?よくある課題と解決策
営業組織が持続的に成果を出し続けるためには、「人材・仕組み・教育・管理」の4軸で課題を明確にし、具体的な改善策を講じることが不可欠です。ここでは、よくある営業の課題とその実践的な解決策をご紹介します。
営業人材不足・スキル不足への対応策
外部リソースの活用
人材が足りない場合には、営業代行サービスやフリーランス営業の活用が短期的な解決策になります。貴社の営業チームと並走できる形でリード獲得・商談支援が可能です。
社内育成の仕組みづくり
中長期では、既存社員のスキルアップが必須です。OJTだけでなく、営業マニュアル、eラーニング、ロープレなどを取り入れることで、自走型営業人材の育成が可能になります。
採用力の強化
採用活動においては、営業経験者に限定しすぎず、育成可能な素養を持つ人材を採用する方針に切り替えることも、選択肢の一つです。
「新規が取れない」をなくす仕組みづくり
顧客ターゲティングの明確化
「誰に営業すべきか」が不明確なまま動くと非効率になります。自社の商品・サービスにマッチするターゲット像を明確にし、ターゲット企業リストの精度を高めることで無駄なアプローチを削減できます。
インサイドセールスの活用
テレアポやメール営業だけに頼らず、Web広告や資料ダウンロードによって獲得したリードに対して、見込み度合いの高い商談を創出する仕組みを導入すれば、営業負担が大きく軽減されます。
営業とマーケティングの連携
広告・コンテンツ・展示会など、マーケティング部門と連携した施策を営業活動に活かし、見込み顧客の質と量の向上を図ります。
営業活動の属人化を防ぐマネジメント手法
プロセス標準化とツール導入
個人のノウハウに頼らず、「誰でも同じ成果を出せる営業プロセス」を構築するために、SFAやCRMツールを活用しましょう。テンプレート・商談履歴・ステータスなどを見える化・共有化することが大切です。
営業KPIの共通化
アポイント取得率・商談化率・受注率といったKPIを定義し、チーム全体でのモニタリングを実施することで、目標のブレを防ぎます。
フィードバック体制の整備
営業チーム間でのロールプレイング・振り返りMTGを習慣化することで、営業力の底上げが図れます。
営業教育・ロープレ・塾の活用と内製化の判断
外部塾・コンサルの導入
外部の営業塾やトレーナーによる短期集中のスキル研修は、即効性があり、営業組織のレベルアップに効果的です。特に「提案営業」や「ヒアリング型営業」においては専門家のフレームを学ぶ価値があります。
内製化のステップ
外部研修に頼りきるのではなく、最終的には自社内で教育コンテンツや指導体制を整えることが理想です。SFAに蓄積したデータや録音ロープレを活用し、成功パターンを仕組み化する動きが求められます。
まとめ:今こそ営業戦略を見直すタイミング
営業活動は「ルート営業」と「新規開拓営業」という2つの軸をどう活用するかで、大きく成果が変わります。
それぞれの違いや強み、そして課題と対策を理解した上で、自社に合った戦略を取ることが、売上拡大と安定成長のカギです。
私たち株式会社スペシャルワンは、広告運用によるリード獲得から、商談化・契約獲得までをワンストップで支援する会社です。
- 「新規開拓営業を仕組み化したい」
- 「ルート営業をもっと効率化したい」
- 「営業組織の生産性を上げたい」
そんな企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。
営業力を最大化するための第一歩を、私たちが一緒に伴走いたします。