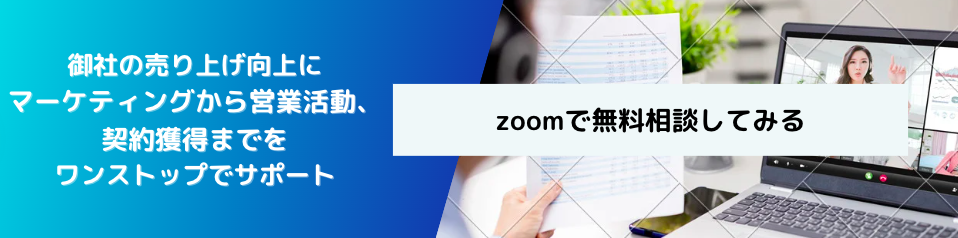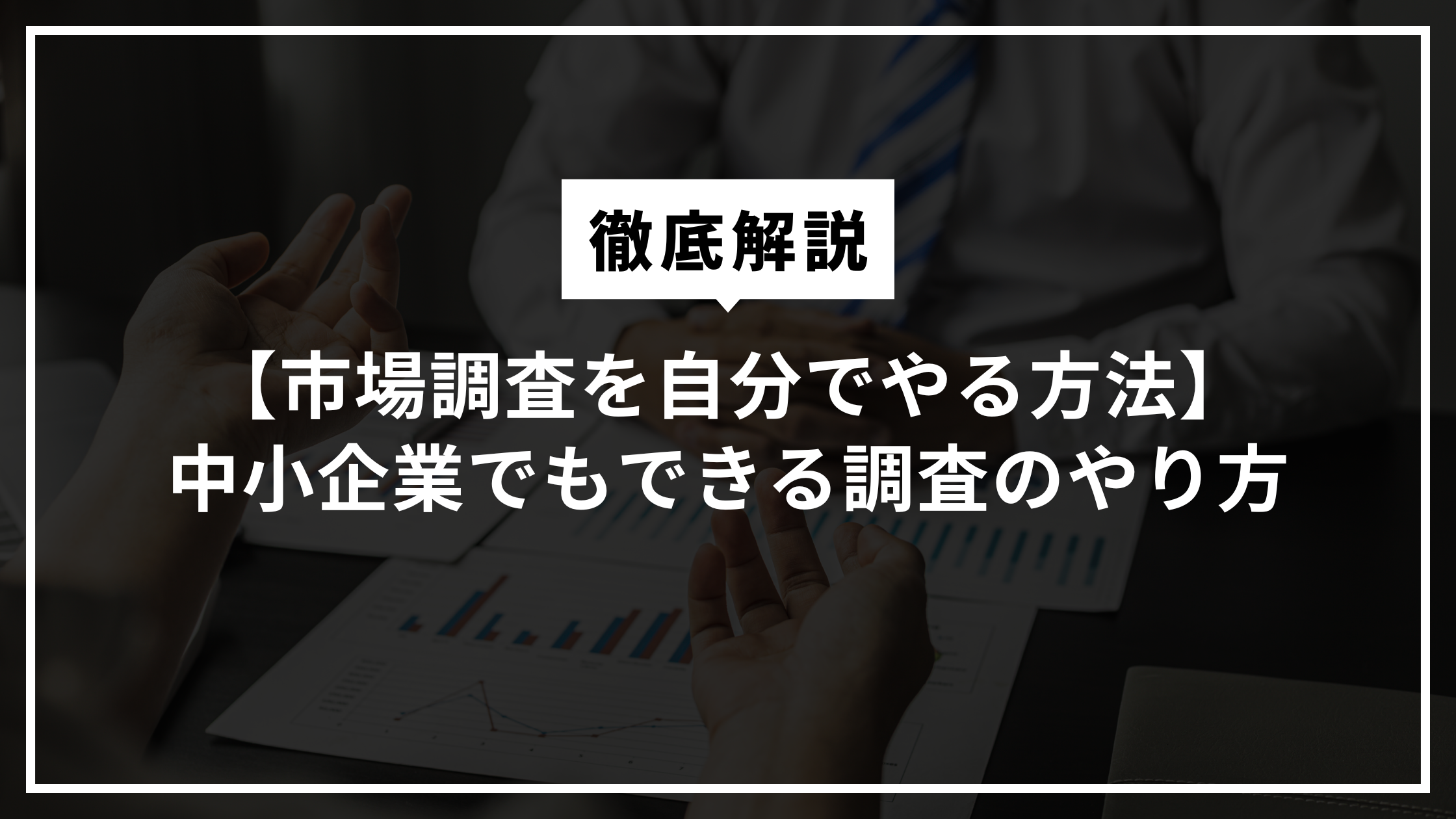「市場調査を自分でやるなんて、本当に可能なの?」——そう思った中小企業の社長様へ。実は、自社で市場調査を行えばコスト削減やスピーディーな仮説検証が可能に。本記事では、自分でできる調査のやり方と、そのメリット・外注の選択肢までを丁寧に解説します。
はじめに
市場調査の重要性と中小企業における課題
市場調査は、企業が市場のニーズや動向を把握し、戦略を立てる上で不可欠なプロセスです。
特に中小企業にとっては、限られたリソースを有効に活用するうえで、市場調査の重要性は非常に高まっています。
とはいえ、リソースや専門知識の制約により、調査に踏み切れない企業も少なくありません。
参考:経済産業省 中小企業白書
市場調査の定義と目的
市場調査とは、市場の規模や競合環境、消費者のニーズなどの情報を収集・分析し、ビジネスの意思決定に活用する活動です。
マーケティング戦略、商品開発、広告施策など、あらゆる企業活動の基盤となります。
市場調査の主な目的
- 市場規模の把握
新たな市場に参入する際の投資判断、ROI計測に活用。 - 競合分析
他社の製品・サービス、価格、広告手法の違いを調べる。 - 顧客ニーズの理解
顧客が本当に求めているものを調査し、開発・改善につなげる。
中小企業が直面するリソースや専門知識の制約
多くの中小企業では、以下のような理由で市場調査の実施が難しい状況にあります。
- 人材不足
調査設計や分析を行えるスタッフが社内にいない。 - 資金的な制限
調査会社に依頼する予算がなく、自社での実施を検討する必要がある。 - 専門知識の欠如
データの収集・分析・解釈に必要なマーケティングリサーチの知識が不足している。
こうした課題をクリアするためには、「自分でできる範囲での効率的な市場調査」の考え方が大切です。
無料ツールや公的な統計データ、ネットアンケートの活用など、今は自社内でも調査を実施できる手段が多数あります。
株式会社スペシャルワンでは、市場調査を含めた広告運用から、リード獲得・契約獲得までを一括でご支援するサービスをご提供しています。
「市場調査を自分で行いたいが不安がある」「プロの視点も取り入れたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
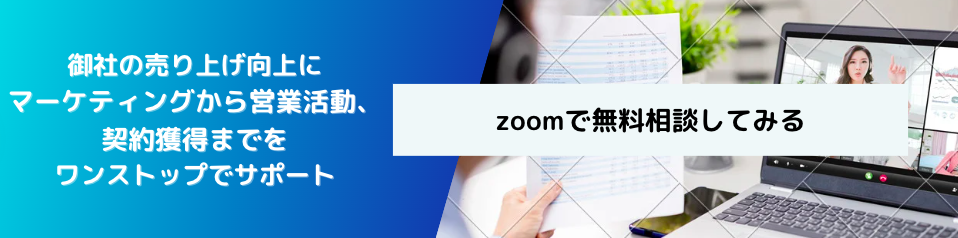
市場調査を自分で行うメリットとデメリット
自分で市場調査を行うメリット
コスト削減
外部の調査会社に依頼すると、規模によっては数十万円から百万円以上の費用がかかることもあります。
自分で市場調査を実施することで、このコストを大幅に抑えることが可能です。
特に、インターネットを活用した無料ツールや既存の統計データの活用により、費用をかけずに基本的な調査を行うことができます。
自社のニーズに合わせた柔軟な調査設計
調査を自分で設計することで、自社の商品やサービスに直結する情報を効率的に収集できます。
例えば、新商品の開発に向けたアンケートや、特定エリアのニーズに関する聞き取りなど、柔軟なリサーチ設計が可能です。
外注に比べて、目的に合わせたカスタマイズがしやすい点は大きなメリットです。
市場への深い理解と迅速な意思決定
調査を通じて顧客や市場、競合について自ら学ぶことで、マーケットに対する理解が深まります。
現場のリアルな声を直接聞くことで、より的確な仮説立てや戦略判断が可能になります。
また、外部委託よりもスピード感を持ってすぐに判断し行動に移すことができるのも強みです。
自分で市場調査を行うデメリット
時間と労力の負担
調査設計、データ収集、分析、レポート作成など、調査には多くの工程があり、一定の時間と手間がかかります。
特に、マーケティングや調査業務に不慣れな方にとっては、業務負担が大きく感じられる可能性もあります。
専門知識の不足による調査精度の低下
質問項目の作成やサンプル設計に専門知識が必要なため、正確なデータが得られにくくなるリスクがあります。
例えば、回答者にとって意味が伝わりづらい設問や、偏った対象者によるアンケート結果は、調査全体の信頼性を下げてしまう要因になります。
バイアスの影響
「こういう結果を得たい」といった無意識の先入観が、調査設計やデータ分析に影響を与える可能性があります。
客観性が損なわれることで、誤った判断や戦略のズレを生む危険性も否めません。
特に、調査対象が狭かったり、身内だけで行った場合は統計的な偏り(バイアス)に注意が必要です。
市場調査の基本的な流れと手順
市場調査を自分で行う際には、目的の設定からレポート作成までの一連のステップを正しく押さえることが重要です。
調査の精度や活用度は、事前の設計と準備で大きく変わってきます。ここでは、初心者でも実施しやすいように、基本の流れとポイントを順を追って解説します。
1. 調査目的の明確化
市場調査を始める前に、まず「何を明らかにしたいのか」を明確にする必要があります。
目的が曖昧なままだと、質問設計やデータ分析がずれてしまい、意味のある結果が得られません。
例えば、
- 新商品開発のため、顧客ニーズを把握したい
- 競合他社との違いを明確にして価格戦略を立てたい
- 自社サービスの満足度を測定し改善したい
など、具体的な課題や仮説を設定することで、調査の方向性が定まりやすくなります。
2. 調査設計
調査目的が決まったら、次は調査の設計です。ここでのポイントは「誰に、どのような方法で調査を行うか」を決めることです。
対象者の選定
調査の精度を左右するのが「誰に聞くか」です。
顧客、見込み顧客、競合のユーザーなど、ターゲット層を正確に設定することが重要です。
たとえば、「都内に住む30代女性」「自社サービスを半年以内に利用した人」など、属性を明確にします。
調査方法の選択(定量調査・定性調査)
調査には大きく分けて定量調査と定性調査の2種類があります。
- 定量調査:数字で結果を把握する方法(例:アンケート)
- 定性調査:意見や感情を深掘りする方法(例:インタビュー)
自分で調査を行う場合は、オンラインアンケートとインタビューの組み合わせが実施しやすく、かつ効果的です。
3. データ収集
アンケート作成と配布
アンケート調査は、自分で市場調査を行う際に最も使いやすい手法です。
GoogleフォームやSurveyMonkeyなど、無料で使えるアンケートツールも充実しています。
質問項目は「Yes/No」や「5段階評価」など、集計しやすい形式を中心にしつつ、必要に応じて自由回答欄も設けると分析に役立ちます。
インタビューの実施
少人数でもいいので、実際のユーザーに話を聞くことで、アンケートでは得られない「本音」が見えてきます。
オンライン会議ツールや電話などで実施可能です。事前に質問リストを用意しておくと、会話がスムーズになります。
4. データ分析
データを収集したら、次は分析フェーズです。
集まった情報をどう読み解くかで、マーケティング施策の精度が変わります。
集計方法と分析ツールの紹介
アンケート結果は、ExcelやGoogleスプレッドシートで集計するのが一般的です。
また、簡易的なグラフやクロス集計、平均値の算出などを活用すると、傾向が視覚的に把握しやすくなります。
定性調査では、「よく出たキーワード」や「印象的なコメント」を抜き出して分類・整理すると、戦略につながるヒントが得られます。
5. レポート作成と活用
最後に、分析結果をまとめて意思決定につなげるレポートを作成します。
- 調査の目的
- 実施方法と対象
- 得られた主な結果
- インサイト(気づき)
- 推奨されるアクション
これらを簡潔にまとめることで、社内での共有や施策立案がしやすくなります。
自分で行える市場調査の手法とおすすめツール
市場調査はプロに依頼しなくても、今では自分で実施できる方法が数多くあります。
インターネットや無料ツールの発達により、中小企業や個人事業主でもコストを抑えて調査を行うことが可能です。
ここでは、自分で市場調査を進める際に使いやすい4つの手法と、それぞれに適したツールを紹介します。
1. デスクリサーチ(既存情報の収集)
デスクリサーチとは、すでに存在する情報を集めて分析する調査手法です。
現場に出向いたり、アンケートを取らなくても、無料で信頼性の高い情報を得られる手段としておすすめです。
インターネット検索を活用した情報収集
Googleなどで「業界名+市場動向」「商品名+ユーザーの声」などで検索することで、
ニュース記事、ブログ、企業のIR情報、調査レポートなど、多くの情報を得られます。
また、口コミサイトやレビューもリアルな消費者の声を読み解くヒントになります。
政府統計データや業界レポートの利用
信頼性の高い情報源として、政府や公的機関が提供する統計データは非常に役立ちます。
- 総務省「統計局」:国勢調査、消費実態調査など
- 経済産業省「特定業種別調査」:業界ごとの最新データ
- JETRO(日本貿易振興機構):海外マーケット情報も充実
また、業界団体が公開している市場レポートや、コンサルティング会社の無料資料なども活用しましょう。
2. アンケート調査
最もポピュラーで実施しやすい市場調査がアンケートです。
定量的なデータ収集が可能なうえ、スピーディーに実施・集計できるのが魅力です。
オンラインアンケートツールの活用方法
以下のような無料/有料ツールを使えば、誰でも簡単にアンケートを作成・配布・集計できます。
- Googleフォーム(無料・カンタン操作)
- SurveyMonkey(条件分岐や自動レポート機能あり)
- フォームズ(日本語UIで中小企業にも人気)
SNSやメルマガ、QRコードを使って配布すれば、対象者に気軽に回答してもらうことができます。
質問設計のポイントと注意点
質問の質が、得られるデータの質を決めます。
「Yes/No」「選択式」「5段階評価」など、分析しやすい形式で設計しましょう。
注意点としては以下の通りです:
- あいまいな表現を避ける
例:「よく使いますか?」→「週に何回使いますか?」に言い換え - 誘導質問をしない
「この商品は便利だと思いますか?」→「この商品の使用感について教えてください」 - 回答に負担がかからない構成にする
回答時間は5分以内を目安に設計すると、回収率が高まります。
3. インタビュー調査
少人数でも、深い情報を得られるのがインタビュー調査です。
顧客の本音や行動背景、感情的な要素など、アンケートでは見えにくいポイントを探れます。
対象者の選び方と効果的な質問技術
対象は、自社商品・サービスの既存顧客、見込み客、業界のキーパーソンなどが理想です。
人選のコツは「多様な属性を含める」こと。1つの視点に偏らない情報が得られます。
質問は「5W1H+深掘り」が基本です。
- 「いつ・どこで・なぜ・どのように・誰が・何を使ったか」
- 「具体的な場面を教えてください」
- 「それを選んだ理由は何ですか?」
録音やメモを取りながら、感情のニュアンスも記録しておきましょう。
4. ソーシャルメディア分析
X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、口コミサイトなど、SNSには日々大量の消費者の声が投稿されています。
リアルタイムなトレンドを知りたいときに有効な手法です。
SNS上のユーザー投稿からのトレンド把握
キーワード検索やハッシュタグで話題の投稿を調べたり、投稿に対する反応の数を見ることで、
ユーザーが何に関心を持っているか、どんな言葉を使っているかを調査できます。
「#〇〇ってどうなの」「〇〇 微妙」などの声は、商品改善のヒントになることも。
専用分析ツールの紹介
以下のようなツールを使えば、より効率的にSNSデータを分析できます。
- BuzzSumo:シェア数や反響の大きいコンテンツを調査可能
- Social Insight:ブランド名での投稿件数、性別・年齢別傾向を可視化
- Keywordmap for SNS:マーケティング向けに特化したSNSリサーチが可能
SNS調査は情報量が多いため、テーマを絞って行うのがポイントです。
市場調査を実施する際の注意点と成功のポイント
市場調査を自分で実施する場合、調査の設計から分析まで自社で対応する分、いくつかの注意点を押さえておかないと、せっかくの調査が意味のないものになってしまう可能性もあります。
ここでは、効果的な市場調査を成功させるために、実施前から意識しておきたい重要なポイントを紹介します。
1. 調査目的のブレ防止
調査を始める際に最も大切なのは、「何のためにこの市場調査を行うのか」という明確な目的の設定です。
目的がブレてしまうと、質問項目も分析方法も曖昧になり、得られるデータの意味が薄れてしまいます。
例えば、「顧客満足度を測定したいのか」「新商品のニーズを把握したいのか」「競合との差別化ポイントを探りたいのか」など、
調査前に具体的なゴールを紙に書き出すことをおすすめします。
目的を明確にしておくことで、調査結果の活用場面や分析軸も定まり、無駄のないプロセスを実現できます。
2. バイアスの排除
自分で市場調査を行うと、無意識のうちに自分に都合のいい答えを誘導してしまうリスクがあります。
このような「バイアス(偏り)」は、調査の信頼性を大きく損なう要因となります。
具体的には以下のような工夫が有効です。
- 誘導的な質問を避ける
×「この商品は便利ですよね?」
○「この商品について、どのように感じましたか?」 - 多様な属性の対象者を選ぶ
自社に好意的な顧客だけでなく、未利用者・離脱顧客などにも意見を求める - 自由記述欄を設ける
回答者が自分の言葉で伝えられるようにすることで、先入観に左右されない情報を得られる
常に客観的な姿勢を保つ意識が、調査の質を左右します。
3. データの信頼性確保
調査の結果をビジネス判断に使うためには、そのデータがどれだけ信頼できるかが重要です。
そのためには、適切なサンプルサイズと調査対象の代表性を意識する必要があります。
- サンプルサイズの目安
最低でも30~50件、可能であれば100件以上を目指すと、傾向が見えやすくなります。 - 代表性のある対象者選定
自社のターゲット層を正確に反映した属性であるかを確認しましょう。
たとえば「20代女性向けサービス」であれば、その層を中心に意見を集める必要があります。
また、同じ条件で複数の人に調査を行い、一貫性のある結果が得られるかを確認することも大切です。
4. 法的・倫理的配慮
市場調査は、個人情報やプライバシーに関わる場面が多いため、法的・倫理的な配慮を忘れてはいけません。
特に自社で調査を実施する場合は、以下のポイントに注意が必要です。
- 個人情報の取り扱い
回答内容に氏名・メールアドレスなどが含まれる場合、利用目的を明記し、同意を取得する必要があります。 - プライバシーポリシーの提示
アンケートフォームや調査メールには、必ずリンクを記載しましょう。 - 回答の任意性と匿名性の保証
「無理に答えさせない」「誰が回答したか特定できない形式」にすることで、回答者の安心感と率直な意見を得られます。 - 守秘義務とデータの保管
調査で得た情報は社内利用に限り、外部に漏らさない体制を整えましょう。
こうした基本的な配慮を行うことで、信頼される調査設計となり、対象者の協力も得やすくなります。
市場調査結果の分析とマーケティング戦略への活用
自分で市場調査を行った後に最も重要なのは、得られたデータをどう活かすかという視点です。
単に数値を眺めるだけでは意味がなく、それをビジネスに役立つ形に変える「分析」と「戦略反映」のステップが欠かせません。
ここでは、調査結果の分析方法と、それをマーケティング施策に活かすポイントを紹介します。
1. データ分析の基本手法
収集したデータを適切に分析することで、仮説の検証や新たな発見(インサイト)につながります。
特に自社で行う場合、シンプルな分析手法を押さえておくと便利です。
クロス集計(クロス分析)
複数の質問をかけ合わせて分析することで、「特定の属性の人がどのように回答しているか」を可視化できます。
例:
「年代 × 商品の満足度」 → 20代は満足度が高いが、40代はやや低い
このように、単純集計だけでは見えない関係性を発見でき、ターゲットごとの施策設計に役立ちます。
相関分析
2つの項目の関係性を数値で確認する方法です。
例:
「広告認知度と購入意欲」の相関を調べる → 相関が高ければ、広告強化で売上が伸びる可能性が高い
ExcelやGoogleスプレッドシートでも簡易的な相関係数を算出できます。
フィードバックの分類・可視化
自由回答などのテキストデータは、キーワードごとに分類・カウントすると傾向が見えてきます。
例:
「高い」「分かりづらい」「便利」などの出現頻度を集計し、ワードクラウドなどで可視化するのも効果的です。
2. 調査結果からのインサイト抽出
調査で得た結果を、マーケティング戦略にどう活かすかが最大のポイントです。
「数値」や「傾向」から何を読み取り、どう行動につなげるかを考えることが重要です。
応用例1:ターゲットの再設定
例:
思っていたターゲット層と実際の利用者層がズレていた場合、広告の配信先や訴求軸を見直す。
応用例2:商品改善
例:
「◯◯が使いにくい」という声が多ければ、UXや導線の見直しに繋げられる。
応用例3:価格戦略の調整
例:
「高いと感じる」という声が多ければ、価格を下げる/機能を追加して納得感を上げるなど、商品企画への反映も可能です。
このように、調査データはそのままマーケティング施策のヒントになります。
調査→分析→施策までの流れを一貫して設計することで、効果的なPDCAが実現します。
3. KPIの設定と効果測定
マーケティング戦略に調査結果を活かすには、「やった結果どうなったか」を測るための**KPI(重要業績評価指標)**の設定が不可欠です。
KPIとは?
Key Performance Indicator の略で、施策の効果を数値で測るための指標です。
広告のクリック率、購入率、問い合わせ数、満足度スコアなどがKPIに当たります。
調査からKPI設定につなげる例
- 調査結果:「○○の説明が分かりにくい」と回答多数
→ KPI:「Webページの滞在時間」「直帰率」をモニタリングし改善効果を測定 - 調査結果:「価格が高いと感じる」
→ KPI:「キャンペーン期間中のコンバージョン率」「CVあたりの単価」で判断
調査結果をもとにしたKPI設定は、施策の改善効果を明確に評価できるという点で非常に重要です。
外部の調査会社に依頼する際のポイントと費用感
市場調査は自分で行うことも可能ですが、調査の精度や業務効率を重視する場合は、プロに依頼するという選択肢も有効です。
ここでは、調査会社に外注するメリット・デメリット、選び方のポイント、費用の目安について解説します。
1. 外注のメリットとデメリット
専門知識の活用
調査会社には、調査設計、データ分析、レポート作成などに長けた専門スタッフやアナリストが在籍しています。
そのため、自分では見落としがちな設計ミスやバイアスも回避し、信頼性の高いデータを得ることができます。
調査結果も、戦略に活かしやすい形でまとめてもらえるため、意思決定の精度が上がります。
コスト増加のバランス
当然ながら、外注には費用が発生します。
「調査はしたいけれど、限られた予算で行いたい」と考える中小企業にとっては、コストと成果のバランスが重要な判断基準です。
費用をかけた分の成果(リード数アップ、満足度改善、CVR向上など)を事前に数値で見込めるかどうかも、外注判断のポイントになります。
2. 調査会社の選び方
自社に合った調査会社を選ぶには、以下のポイントをチェックすると安心です。
信頼性や実績の確認ポイント
- 実績のある業界や企業規模:自社と似た市場や規模での経験があるか
- 公開されているレポートや事例:サイトやパンフレットに具体例があるか
- 調査手法の幅広さ:定量・定性両方に対応しているかどうか
- 担当者の対応力:ヒアリングが丁寧か、理解が早いかも重要
可能であれば、事前にミニヒアリングや資料請求を行い、比較検討するのがおすすめです。
3. 費用相場と予算設定
外注費用は、調査規模や手法によって大きく異なります。以下は一般的な相場感です。
アンケート調査(定量調査)
- ネット調査(100名~300名程度):10万円〜50万円
- 紙媒体・郵送調査:30万円〜100万円(配布・回収コストが高い)
インタビュー調査(定性調査)
- グループインタビュー(座談会形式):1回あたり20万円〜50万円
- 1on1インタビュー(10名程度):30万円〜80万円
フルカスタムの市場調査パッケージ
- 設計〜報告書作成まで一式:50万円〜200万円以上
このほか、分析レポートや資料作成の追加費用がかかる場合もあります。
予算を立てる際には、「目的」「規模」「納期」に応じて調査内容を調整しながら、段階的に導入する方法も有効です。
まとめ:自社に最適な市場調査の方法を選択し、ビジネス成功へ
市場調査は、自社の商品・サービスを**「求められるもの」に変えていくための最も基本的で強力なマーケティング手法**です。
中小企業でも、自分で実施できる方法は多く存在し、ツールや情報源を上手く使えば、低コストかつスピーディーに価値あるデータを得ることができます。
今回紹介したように、調査の目的を明確にし、手法を選び、分析と戦略に落とし込む流れを押さえることで、
「調査して終わり」ではなく、「成果につながる調査」が実現できます。
一方で、リソースが足りなかったり、分析や活用に不安があるときは、外部のプロに相談するのも効果的な選択肢です。
重要なのは、「すべてを自分でやる」か「すべてを任せる」かの二択ではなく、自社に最適なやり方を選ぶ柔軟な視点です。
株式会社スペシャルワンでは、「市場調査の一部は自分でやりたいけれど、戦略に落とし込む部分は相談したい」といった企業様にも、
広告運用から契約獲得までを含む一気通貫のマーケティング支援サービスをご提供しております。
**「最適な市場調査の進め方が知りたい」「今の施策を改善するヒントが欲しい」**という方は、
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
貴社のマーケティング活動が、より効果的で、成果につながるものとなるよう、私たちが全力でサポートいたします。